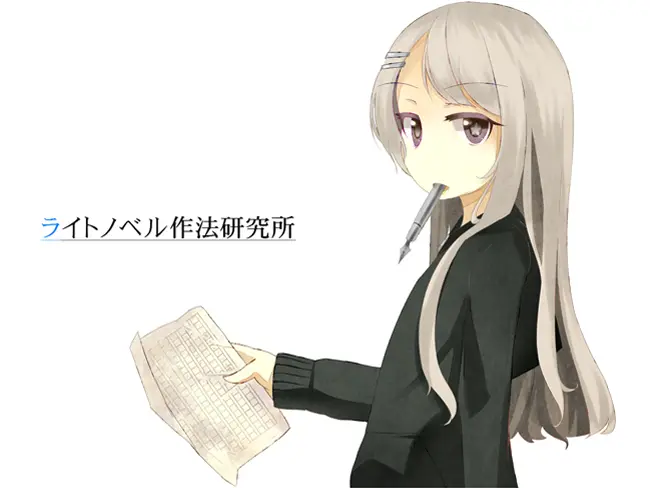トピックの字数制限の関係で「本文」「付言前編」「付言後編」の三つに分けます。「本文」「付言後編」は下記リンクからどうぞ
【付言 バード女史の行動・考え方に関する感想】
本文は「創作資料としての評価」なので、それとは外れるが、バード女史の行動・考え方の感想を三つ述べる。本書全巻を通じて、博識で公正なバード女史の言動に矛盾や違和感があることが多かった。
なお訳者解説によると、本書の執筆が開始されたのは、1898年10月末で、バード女史の英国帰国が1巻の序によると1897年とあるので、バード女史の認識が「旅の最中」なのか、「帰国後」なのかの判断が付かないことがある。
バード女史の旅行記は、本書以前に、アメリカが旅先の『ロッキー山脈踏破行 』(平凡社ライブラリー、小野崎晶裕訳)、インドのラダック地方が行き先の『チベット人の中で』(中央公論事業出版、高畑美代子、長尾史郎訳)を読んだ。この両書では、バード女史が旅先の習慣に反するふるまいをし、キリスト教を押し売りし、住人のプライベート空間に侵入する印象はなかった。だが、本書を読むと「バート女史とはこんな人だったっけ?」との感を禁じ得ない。
1、公正なバード女史が、なぜ中国の慣習に反し、現地民の憎悪を買う「覆いのない轎」に乗り続けたのか?
訳者解説によれば、バード女史は「敵対的な住人からの、彼らからすれば当然の攻撃に何度も遭遇」(2巻384ページ)している。しかも、バード女史を標的にする暴動・襲撃が2度も起きていている(第1の襲撃は1巻336ページ‐342ページ、第2の襲撃が2巻75ページ‐80ページ)。しかも2度目には一時気を失い、1年間後遺症に悩まされるほどの重傷を負わされている(1度目も「みみずばれ」程度の軽傷を負わされた)。
その原因を、バード女史自身が「中国の慣習に反して『覆いのない轎に乗ったこと』」と「日本製の笠、中国服、英国製の靴という服装」と繰り返し書いている。
バード女史がこの自己分析に至ったのはいつなのか? 旅の最中、特に2度目の襲撃前なのか? それとも2度目の襲撃後か? それでは遅過ぎるからないだろうが、帰国後のことなのか? そもそもこの「自己分析」は当たっているのか? 後述の通り、バード女史の旅に協力した現地駐在の宣教師たちは、バード女史の「轎」「服装」を問題視しておらず、対応がチグハグで不自然。
もっとも2巻第二十七章79、80ページには2度目の襲撃後、
官吏は[秘書を通じて]彭県での礼の失する事件について遺憾の意を表したが、その一方で、住民が覆いのない轎も外国の笠もこれまで見たことがなかったのでと言って、連中を一部弁護もした。
とあった。バード女史が、襲撃の原因を「轎」と「笠」だと、この時点まで認識できていなかったのであれば遅い気はする。
1度目の襲撃前に「覆いのない轎」が現地民の憎悪をこれほど買うとまでは予見できなかったとしても、第1の襲撃後も「覆いのない轎」に乗り続けたことが、本書最大の疑問。
バード女史はこれほどの仕打ちを受けながら、して当然な中国や中国人を憎悪・侮蔑することなく、しかるべき役所へ旅行許可から当然の権利である抗議の申し立てもせず(抗議しても状況が終わったあとであれば無意味だし、下手に抗議すると、安全を理由に帰国を説得される恐れがあったのでは? と勝手に想像してはいる)、淡々と事実を記しているほどの、公正でタフな旅行家である。いたずらに現地民の憎悪をあおる言動を取るとは考えにくい。
しかも、バード女史は1巻第二十三章392ページで、おおむね次のように記してさえいた。
- 中国人暴徒の暴力に苦しめられてきたとし、それは官吏の煽動ではないにせよ、「黙認」があったと信じているとしていること。
- 暴徒への「黙認」に対し、正式な苦情を申し立てる機会は何度もあったが、官吏の大変さに同情していたため、申し立てを行わなかったこと。
- 中国の慣習を知らず、外国人の軽はずみな行動が排外感情を爆発させることがある。中国の慣習に反し、「覆いのない轎に乗ったこと」を自戒していること。
- 外国人が中国人暴徒の暴力による損害(身体・所持品)が出て、正式に抗議をすると、自国の領事もこれを支援する。結果、官吏は現場から遠く離れていても、責任取らされて左遷されること。
帰国直前まで西洋人と全く接触しなかったのではなく、第1の襲撃後、第2の襲撃までの間に、2度も現地駐在の宣教師と会っている(詳細後述)。宣教師に会った際にそれまでの旅について話さなかったのか? 話さないのは不自然だし、宣教師たちもバード女史が現地民の憎悪を買って襲撃を受けたと聞けば、轎や服装について、何かしろの忠告をしたのではないか? それにバード女史は現地駐在の宣教師たちが、中国の慣習と礼儀を順守するよう努めて、中国人を怒らせないようにしていることを繰り返し書いている。なのに、なぜそれにならわなかったのか?
バード女史は対中伝道の宣教師向けにこのような忠告を書いている。(2巻第三十九章「中国のプロテスタント系伝道会に関する覚書」334ページ)
バード女史は、中国で西洋人女性が避けるべきものとして、「覆いのない轎」「ぴったりとした婦人用胴着など身体つきがわかるような恰好」「中年中国人女性の付き添いなしに、町や村を歩いたり、住民の家を訪問したりすること」などを細々と例示した。
その上で、中国人とのトラブルの例として、「西洋の少女がつばの広いふわっとした帽子をかぶって現れると、聞きたくもない言葉を浴びせられ、帽子に鳥や昆虫などが投げ込まれるといった嫌がらせを受ける羽目になる」と強い調子で警告した。
中国内陸宣教会や英国教会伝道協会(四川省)の宣教師は中国式服を着用することで、現地民の反感を買わなくなったとして、伝道会に対し、中国式の制服を採用するように、強く提言した。
本書全巻通じて、バード女史は「覆いのない轎」に乗ることは、「旅行者にとっては些細なふるまいでも、現地民からすれば『自分たちの習慣・文化・伝統・価値観を破壊する「重大な攻撃・敵対行為」』と認識される」との自覚があったのではないか? とも感じる。
現に、バード女史は、四川駐在の宣教師たちに対する中国人の感情について、以下に記す正確な認識を持っていた。
- 四川の住人の間には、宣教師が子供の目や心臓を薬として用いるとの盲信が広がっており、「外国の悪魔」「子供食い」とみなされていること(中国人の盲信には、バード女史は同情的ですらあった)。
- 目や肌の色、座り方や手の動かし方など、すべてが嫌悪の気持ちを引き起こしていること。
- スパイや政治的手先ではないとしても、西洋の宗教(キリスト教)を教えるためにやってきたこと。
- キリスト教は、中国人の国民性、孔子が広めた素晴らしい社会秩序、尊敬に値する純粋な国民生活と先祖への忠誠を破壊する、忌まわしいものであること。(1巻第二十三章393ページ)
それ故に、「現地の慣習に反する振る舞いをすれば、身に危険が及ぶ」ことが明確になった、第1の襲撃の後も、なぜ「覆いのない轎」に乗り続け、日本の笠をかぶり、英国の靴を履いたのか? 特に憎悪を向けられる都市部・主要街道のときだけでも、轎に覆いを付ける、全身中国服で固めることをしなかったのか? 実際、第2の襲撃を受ける直前の、2巻二十七章58ページでは、以下のように都市部に入ることを警戒している。なのに轎と服装については、かたくなだったのか? 無邪気なのか? よく分からない。
梁山[県]の暴動(引用中。第1の襲撃)以来、私は大きな城郭都市には足を踏み入れないようにしてきた。(太字朱字化引用者)
バード女史が、バリバリの西洋キリスト教至上主義者で、キリスト教と西洋近代文明を礼賛し、中国人に対し、侮蔑・憎悪・差別をあらわにする人であれば、「郷に入っては郷に従え」は当然のこと、従わなかったのが悪い、と切って捨てただろう。「2」「3」も含めて、このような疑問を持つことはなかったかと思われてならない。
2、バード女史の服装・行動に対する宣教師たちの対応
バード女史の中国四川での旅は、「伝道状況の視察」との目的があり、現地駐在の宣教師の協力に拠っている。フランス領事が暴動被害について、不当に高額な賠償金を得たこともあり、本書の旅の時期には、四川省都市部の知識層間で排外感情が強い。にもかかわらず、西洋キリスト教世界と中華世界との衝突の最前線にいる、協力者の宣教師たちの対応が、以下のように甘くてチグハグな感じを受ける。
・トンプソン宣教師
出発地、万県で、バード女史の轎をはじめ、四川の旅全般を手配(1巻第十八章)。しかも1日目はバード女史に同行。1巻第十六章271、272ページでは、トンプソン宣教師の伝道所が現地民の憎悪の対象になっている。
バード女史は、自身の到着1カ月前に、トンプソン宣教師の伝道所が暴徒の襲撃にあったことを書き留めている。「外国の悪魔」が井戸から水を抜き取り、この都市の「幸運」の蟹を盗んだ、と信じていた暴徒は、伝道所の外に集まり、建物を焼く、「外国の悪魔」を皆殺しにすると脅迫した。暴徒は最終的には、官吏により引き上げさせられた。しかし、官吏はトンプソン宣教師の伝道所を、子供たちの目を取ろうとして子供たちを殺害し、死体を裏のタンクに捨てたと激しく非難した。非難した官吏は、バード女史の到着時には退職したとのこと。文脈的に、伝道所を非難した官吏は、事件の責任を取らされたように感じた。
トンプソン宣教師は、バード女史の旅の初日に同行し、手配がうまくいっているのかを確かめるほどの慎重な人だ。上記の通り、極めて緊迫した情勢下なのに、バード女史の護衛を手配していない。清国官吏によるバード女史の安全保障が機能する、と判断していたのだろうか? バード女史には役所から派遣された差人(付添人)が同行している。この差人が旅行許可証(護照=旅券)を振りかざせば騒動は収まる。ただ、2度の暴動・襲撃時には真っ先に差人が逃亡しているし、他の場合も含めて官吏もギリギリの状況になってようやく出張っている。旅の最終盤を除いて、清国官吏がバード女史の安全を積極的に確保しようとしている印象はない。なお、バード女史の記述からの勝手な憶測だが、外国人への悪印象、職務不熱心、暴徒への恐怖があったにせよ、現地の官吏は対外条約順守の北京の中央政府と、地元民(特に有力者)の感情との板挟みになっていたのではないか? 外国人の味方をしたと地元民の反発を恐れたのでは? とも考えられる。
どの国でも知識層は礼儀作法に厳しいが、中国は特に厳しい。バード女史も、こう書いている。なのにバード女史が中国の作法に反し、「覆いのない轎」に乗り、日本の笠をかぶり、英国の靴を履くことを止めていない。トンプソン宣教師はバード女史の旅の初日に同行し、これも問題ないと判断したのだろうか?
私の体験の限りでは、宣教師は、ごく一部の例外を除いて男女の別なく、中国の慣習と礼儀を、知っている限り順守しようと一生懸命だったのだが。また住んでいる地方の人々を何とかして怒らせないようにしていたのではあるが。(1巻第二十三章393ページ)
・ウィリアムズ宣教師
バード女史が、第1の襲撃と第2の襲撃の間に訪れた保寧府駐在。同府でバード女史の廟撮影をきっかけに、バード女史への憎悪が向かう場に同席(2巻第二十五章18、19ページ)。バード女史の写真撮影が、中国の慣習と礼儀に反する、とこれほどまで強く現地民に認識された場面にいながら、バード女史が「覆いのない轎」「日本の笠」「英国の靴」で旅を続けることに忠告した形跡がない。
ウィリアムズ宣教師とともに、瘟神(疫病の神)廟を訪れたバード女史は、その際、轎かきの勧めと手助けで、開けっぱなしの廟の舞台に上がって撮影した。戻ろうとしたところ、一人の文人から、この行為に対しウィリアムズ宣教師が激しくとがめられた。その翌日、女性宣教師の従者たちは、家から出ないよう彼女らに懇願し、通りや茶店ではこの「不埒な行為」が神の憤りをかうだろうという話でもちきりになった。また、「外国人を皆殺し」にするという話までされていた。この行為が原因で「外国の悪魔!」(洋鬼子)や「外国の犬!」(洋狗)といった激しい叫び声が上がり、バード女史はウィリアムズ宣教師から、「これほどひどい叫び声は聞いたことがなかった」「この叫び声と住人を駆り立てる憎しみは、都市に外国人が長く滞在するほどひどくなるように思われる」と聞かされた。
この撮影は、中国人の轎かきに勧められてのこと。轎かきは雇い主のバード女史を喜ばせることにしか念頭になく、現地民、特に文人の外国人への憎悪まで考えが至らなかったのかもしれない。にしても、同座しているウィリアムズ宣教師も撮影を制止しなかったことからすると、ウィリアムズ宣教師は撮影には問題がないと判断したのだろう。バード女史も、轎かきが撮影に不安の色を示し、もしくは止めるように懇願され、同行の宣教師から制止されれば、それを振り切ってまで撮影を強行するとは考えにくい。
・ホーズバラ宣教師夫妻
梓潼から灌県までの間、バード女史に同行、途中の羅家場で第2の襲撃に遭遇。バード女史から、1度襲撃を受けたことや直前の保寧府で写真撮影がきっかけで強い憎悪を向けられたことを聞かされなかったのか? 轎に覆いを付けることや、せめて目立つ笠だけでも脱ぐことを忠告しなかったのだろうか? ホーズバラ夫人は、自分の中国服をバード女史に貸すことをしなかったのだろうか?
2巻第二十七章76ページの襲撃とその後の箇所を読んでも、中国の作法にかなった服装・轎と思われるホーズバラ宣教師夫妻には暴徒の被害があった様子はない。バード女史が「覆いのある轎」に乗っていれば、暴徒に取り囲まれて罵声を浴びせられても、重傷を負わされるまではなかったのではないか? ホーズバラ宣教師夫人の判断で、渡河を下手に回ったのは暴動を恐れてか? 単に混雑していたからか? の別は判然としない。バード女史もホーズバラ宣教師夫妻の忠告なら、聞き入れたものと思われる(第2の襲撃は75ページ‐80ページ)。
『中国奥地紀行』(全2巻)
イザベラ・バード著
金坂清則訳
平凡社ライブラリー