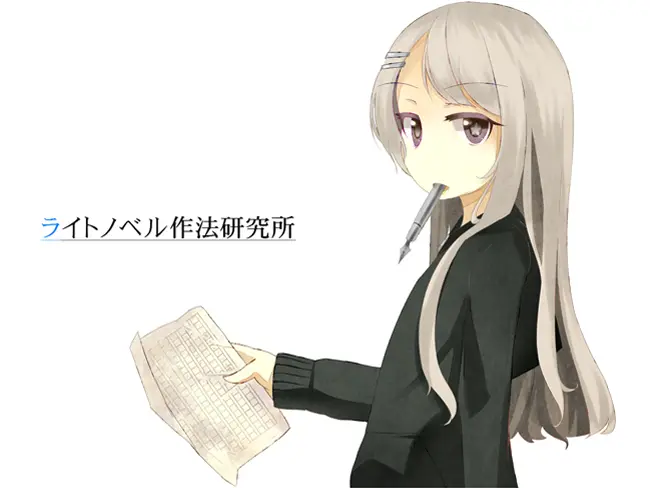『日本人が知らない本当の道教』
草思社文庫
三多道長 著
【総評】
本書は、その大半が道教の神々の解説に終始しがちな従来の「道教本」とは一線を画し、「道教的生活の実践」に重きを置いていた。そして、読む価値のあった点は以下の2点である。
・道教の「吉凶禍福」「趨吉避凶(福を招き、災いを避ける)」の基本的な考え方への理解が深まったこと。
・中華風ファンタジー好きからすると、道教の修行、神々・死者との交信が取り上げられた「第二章」、「第五章」後半、「第六章」は、オカルト系中華風ファンタジーの副読本として価値があること。
ただ、本書を読んだ結果、以下に示すように、内容とカバー・帯との間に強い違和感や期待外れ感を覚えることとなった。
【視点の偏りに対する疑問】
1、 期待された「日本視点」の欠如
本書のカバーには「日本人が古くから大切にしてきた「人として宇宙の法則に逆らわずに調和する道教的生き方」をあらためて思い起こす一冊」とあり、帯には「日本人唯一の現役道士」と銘打たれているにもかかわらず、記述の視点の割合は台湾が圧倒的で、日本と台湾の比率は1対9程度に感じられた。
しかも、日本のことなのか、台湾のことなのかも、一見しただけでは分からず、よく読む必要がある箇所も散見された。
著者・三多道長氏の経歴から、日本視点から道教を語ることを強く期待していたが、この期待は裏切られたと言わざるを得ない。過度に理想化された「日本人の美徳」と道教とを強引に結びつける記述(詳細後述)も多く、違和感を拭えなかった。道教がキリスト教ほど日本と相容れぬ存在ではなく、日本文化の多くが中国に由来するとしても、道教は日本人にとって「中華圏の民族宗教」という「外国の宗教」のイメージが強い。なのに、それを無理やりに結び付けていると強く感じた。
2. 日本における道教の「位置づけ」への言及不足
仏教寺院や神社ほど道教寺院が身近ではない現代日本において、一般の日本人が仏教僧や神職に、葬儀や七五三といった儀式を行ってもらうように、道士に儀式を行ってもらう機会は極めて少ない。
「日本は他国の文化を取り入れて自分たちに合わせて変容させるのが特徴」とされるが、道教が変容することなく日本に定着したならば、台湾と同様に道教寺院が至る所に存在し、道士の姿を誰もが容易に想像できるはずである。しかし、現実はそうではない。
一般的な日本人にとって、道教はあくまで「外国の宗教」である。道教が日本に入ってきたのならば、なぜ仏教寺院ほど一般的ではないのか。また、道教が日本に合わせて変容し、根付いているのなら、具体的にどのように根付いているのか。
「日本と台湾を行き来していると、それぞれの国の宗教間の違いがよく見えてきます」(52ページ)や、「なぜ徳川家康は風水にハマったのか」(146ページ)といった記述があるにもかかわらず、「日本と道教とのかかわり」、すなわち徳川家康などの時の権力者や日本仏教、神道と道教との具体的なつながりについての記述は極めて断片的で薄い。この日本における「道教の位置づけ」という肝心な視点が抜け落ちているため、全体としてチグハグな印象を禁じ得ない。
「道教的生き方」を実践することと、日本の仏教寺院、神道神社を参拝することの関係を含めて、これらについて1、2章当てて詳述してほしかった。
結果として、道教の基本的な考え方(吉凶禍福、趨吉避凶など)は理解できるものの、「現代日本人が『無理なく』『日本で』道教的生活を実践するにはどうすれば良いのか?」という、本書が最も訴えるべき視点が薄く、読者に「自分でもやってみよう」という意欲を喚起させるには至らない。経済的・肉体的・精神的な負担が過度になる可能性についての言及もなく、理想ばかりが先行し、現実との折り合いが見受けられない。日台を頻繁に往復する著者には気にならないのかもしれないが、修行道具や線香などの入手性一つとっても、台湾と日本では環境が大きく異なる。
【戦前日本の家族関係を理想化しすぎている】
1、「津山事件」が示す戦前の現実
三田氏は、現代日本における親子の殺害事件の背景として、戦後に失われた伝統的な日本人の美徳を挙げている。その美徳とは、「目上を敬い親に孝行する」といった精神性や「縦の絆と横の絆」を大切にする精神性であり、これらが失われたことが、欲望や享楽を優先する現在の社会につながったと論じている。さらに、先祖や親を大事にすることで「福の連鎖」を作り、それを子孫に繋ぐという仕組みは、道教的な生き方であったと主張している(35、36ページ)。
これは本書全体の「前提」になろうが、相当戦前の日本社会を理想化していると、断ぜざるを得ない。
しかし、三多氏が理想とする戦前の、1938年(昭和13年)に岡山県の農村(農村部は、都市部に比べて信心深く、絆を大切にし、「純朴」なイメージがあるのでは?)で、死者30人を出す「津山事件」が発生している。この「津山事件」は、1人の人間がわずか1時間半の間に、28人を殺害(のち2人死亡)した事件で、しかも第一の被害者は【犯人の祖母】である。
戦前の日本人が、三多氏の言うような人々なら、「津山事件」のような事件は、到底起こりえないのでは?
負傷者数が桁違いで、事件の背景も異なるので単純な比較は無意味だが、戦後の1995年(平成7年)に起きた「地下鉄サリン事件」ですら、死者数は14人で、「津山事件」はその2倍である。2019年(令和元年)に発生した「京都アニメーション放火殺人事件」発生まで81年間、戦争を除く同一犯罪事件として、近代以降日本での死者数第一位の事件だった。
犯人が自殺する直前にしたためた遺書には、祖母への【早くに両親を亡くして育ててもらったことの感謝と、殺害したことの謝罪】はあったが、虐待を受けた恨みはなかった。下記、Wikipediaに当該遺書(異常な精神状態でしたためられたものなので、どこまで信じられるかは別として)が掲載されている。これを読む限り、「犯人は犯人なりに、祖母を大切にしていた」との解釈も成り立つ。犯人が祖母から虐待を受けていた、のであればまだ事件が起こることは分からなくないかもないが、犯人と祖母との関係は「悪い」感じは受けなかった。
この事件は、三多氏の述べる「絆を大切にする精神性」が普遍的なものでなかったことを示唆する。
参考 Wikipedia『津山三十人殺し』
2、「尊属殺人罪」の存在
また、刑法(明治45年法律第45号)において、親殺しを加重処罰する「尊属殺人罪」の規定が、1995年の口語化まであった(1973年に最高裁が違憲と判断、以後不適用)という事実は、法律が「親殺し」を想定していたことを意味する。もし日本人が三多氏の言うような「美徳」を持つ人々ばかりであれば、「親殺し」を想定する必要のない社会であったはずであり、「尊属殺人罪」の規定自体が不要だったと考えるべきである。
これらの事実は、三多氏が前提としている「戦前の日本人の美徳」が過度に理想化され、現実を反映していない可能性を強く示している。
【「道教至上主義」ないし「道教原理主義」的な印象が強い】
道士が著した本であるので当然と言えば当然だが、本書は何でもかんでも道教に結び付けているために、行間の端々から「道教至上主義」「道教原理主義」的な印象を強く感じた。
確かに、経済的に困らず、子や孫に囲まれて、健康で穏やかな老後、は確かに多くの人が理想とするものだろう。だが、すべての人が良縁に恵まれて伴侶を得られるわけでなく、子や孫に恵まれるわけではなく、結婚や子や孫を欲するわけでもない。幸せの形は人それぞれのはずで、別の形での「幸せ」もあるだろう。「三多氏が考える『幸せ』」を押し売りされているとも感じた。
また、台湾人が自然と道教的生活を実践しているのは分かる。だが、現代の生活と、道教的考えが相反する場合に、どう折り合いをつけるのか? という面も見えてこなかった。
三田氏は、道教の実践者である華僑系の航空会社の事例として、経営者が採用に際して面相学を用い、「負の気があまりない」顔立ちの人を選別している点を挙げている。さらに、全社員に吃素(菜食)を徹底させることで負のエネルギーを極限まで減らし、不運な飛行機事故を発生させにくくするという道教的ロジックを紹介し、この航空会社がトラブルが少ないと評判であることを伝えている。また、三田氏はこの航空会社が日台間の往復で愛用することになったとも述べていた(189ページ)。
これを日本の企業が行った場合、採用時の差別として問題視される可能性が高い。また、社員に対し「道教の信仰」を強要することは、「信仰の自由」を保障する日本国憲法(第20条)に反する可能性がある。さらに、不十分な知識で厳格な菜食主義(吃素)を強要すれば、栄養失調を引き起こし、かえって心身不健康な乗務員が航空事故の原因となるリスクすら否定できない。
本書全体を通して、三多氏の論は理想ばかり立派で、道教的正しさ(これには疑問があるが、「「善意」が招く災いへの危惧」の項で述べる)に無邪気に喜び、その弊害、特に現代日本社会での価値観や法的側面で衝突する可能性を考慮していない、と感じた。
【書名、章名が攻撃的】
本書の書名や章名に「日本人が知らない」「間違いだらけの日本」といった言葉が冠されていることは、読者に攻撃的な印象を与えかねない。
これは本書全体に感じられる傾向だが、特にその書名や章名は、三多氏が師匠から受けた教えと矛盾しているように思えてならなかった。
三多氏は、師匠の教えに基づき、人に害をなす人物と接する際、猛然と立ち向かい罵倒することを避け、場の空気や流れを荒立てないようにするべきだと説いている。その上で、自分のリズム(呼吸)を崩さず、確固たる意志を持って、礼儀正しく毅然とした態度で接することが、相手による危害の拡大を防ぐことにつながると主張しているからである。(99、100ページ)
【「善意」が招く災いへの危惧】
道教では、「徳を積むことのよさや必要性をわかっていて実行しない人より、利己的な気持からやっていることを自覚しながらも実際に実行している人のほうが、はるかに吉につながる生き方をしていると言えます」(117ページ)とのこと。
以下の2例のエピソードは、一見すればほほえましいことだ。ただやり方を誤ると、施した側、施された側共に「善意がかえって災いを招くのでは?」との危惧を感じた。「利己的な考えでも徳を積めば吉になる」との考え方は分かるが、「善意」での行いがかえって「災い」の循環になった場合は、「徳を積む」ことになるのか? そうなった場合、道教ではどのように考えるのか?
1、道教寺院で「一人紙コップ一杯」のルールを曲げて、「お婆さんに『水筒一杯』のお茶を施した」こと(100ページ)
三多氏は、台湾の寺院で無料の養生茶を振る舞う際、ボランティアが規則に従い水筒を差し出したやせ細ったお婆さんの要求を拒否した事例を紹介している。それに対し、ある道士が、規則を曲げて水筒にお茶を満たし、「根源にあるはずの愛心を失わぬこと」や「人のために法がある」という考えの重要性を説いた。
この特別扱いが、「困っているお婆さんだから」と、周りが理解し、受け入れてくれれば問題ない。ただ、「なぜあのお婆さんだけ特別扱いするのか!?」と、以下のような弊害を生む可能性がある。その場合は、この道教寺院と道士はどのように対応するのか?
・一人に水筒一杯分のお茶を施したため、求める人全員に「水筒一杯」のお茶を施さなければならなくなった。それが可能なら良いが、紙コップ一杯なら100人に施せていたものが、20人にしか施せなくなった。あふれた80人から受けられなかったことの不満が出た場合。
・「紙コップ一杯」が、「水筒一杯」になったのだからと、「10リットルの水タンク一つ分」、さらには「給水車一台分」と、段々と求められるお茶の量が増えた場合。
・このエピソードでは「お婆さん」なので想像しにくいが、もし特別扱いを受けたのが「子供」だったら、ほかの子から「ずるして特別扱いを受けた」といじめられないか?
2、三多氏が公園の池で魚にエサをあげたこと(113ページ)
三多氏は、池で魚が食べるものがなくゴミを突いている様子に心を痛め、コンビニで購入した大量の餌を施した。その直後に飛行機に乗った際、エコノミークラスの機内食が切れたおかげで、ビジネスクラスの機内食を食べることができたという幸運を経験したと語り、善行と吉事の連鎖を暗示している。
上記の通り、三多氏は魚に餌を施した結果、「エコノミークラスなのに、ビジネスクラスの機内食を食べられた」と無邪気に喜んでいる。ただ、この池の魚がどのようなものだったのかは書いてなかったので分からないが、これも下記のような弊害には言及がなかった。
三多氏は、わざわざコンビニへ「魚の餌」を買いに走っているところから推測するに、「魚に人間の食べ物を与えてはいけない」との見識をお持ちのはず。ゆえに、「不適切な餌やりになっていないのか?」との疑問を禁じ得ない。「池のゴミを拾う行為」であれば、何の疑問もなく「徳を積んだ」と理解できたはずである。
・公園で飼われている魚であれば、管理者が与える適切な量の餌を無視した過剰な餌やりは、魚の寿命を縮める可能性がある。
・野生の魚であれば、人間が餌を与えることで魚自身の採餌能力を奪い、自ら生きる力を弱めることにつながる。
・それが駆除対象の外来魚であれば、餌を与える行為は生態系を乱し、在来種を駆逐する手助けとなる。
・野生動物の餌付けは、人間との適切な距離を崩し、最終的にその動物が「害獣」として駆除の対象になりかねない。
「利己的な考えでも徳を積めば吉になる」という考え方は理解できるが、「善意」による行いがかえって「災い」の循環となった場合、道教ではどのように考えるのかという、より深い考察が必要である。読者にこの疑問を提起するために、この2例を示したのでは? との「好意的解釈」も成り立つ。だが、三多氏の論考には不十分さを禁じ得ない。
【道士の修行生活、台湾の道教的生活の記述の不十分さについて】
本書を読むと、「詐欺」とまでは言えないが、せっかくの日本人道士の著書にもかかわらず、書名、カバー、帯、目次と内容・視点とが、期待とは微妙にズレた感じが強い。以下の点が詳述されていれば、満足感もあり、別の感想を持てたのでは? と感じてならない。まったく記されていなかったわけでないが、記述が断片的でよく分からなかった。より掘り下げてほしかった。
・道教寺院での儀式・行事及び道教寺院での道士の修行生活の詳細。柿沼陽平氏著『古代中国の24時間』(中公新書)のような感じで、道士の一日の日課、道教寺院の一年間を詳述してほしかった。
・道教寺院の構造詳細(建物の配置、建物内の間取り、祭壇のしつらえ)。
・「台湾歳時記」の感じで、台湾人が行う一年間の道教の儀式・行事の詳細。
・台湾人が自宅で祀っている道教祭壇のしつらえ。
・吃素実践の仕方の詳細、吃素の具体的程度、吃素料理の具体的献立。
・台湾及び中国大陸での道教聖地の詳細な紹介(195~197ページの2ページ半では少なすぎる)。
・日本人が台湾・中国大陸など中華圏を訪れた際、道教寺院を参拝するときの詳細な作法。
・台湾・中国大陸における、道士や道教徒が孔子廟や仏教寺院を参拝することの可否など、道教と、儒教・中国仏教との関係詳細(本書では台湾の「道教寺院」も、「仏教寺院」も、単に「お寺」とあり、分かりづらい。一応、日本の「神仏習合」に近いものとは想像している)。


 Wikipedia
Wikipedia