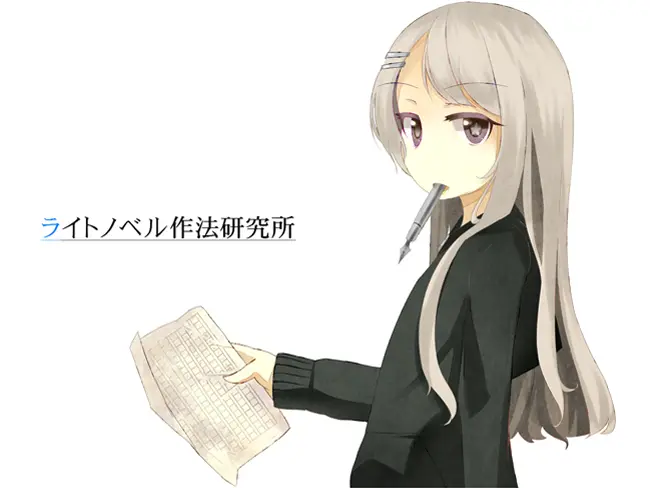『皇帝食 - 不老不死を求めて 古くて新しい“生命の料理”哲学』
石橋幸(龍口酒家) 著
南條竹則 監修
スローガン
総評
書名やうたい文句から、歴代中華皇帝の食に関する具体的なエピソードや、「満漢全席」をはじめとする歴史的料理の献立・調理法に関する深い考察を期待して本書を手にした。しかし、率直に言って、その期待は大きく裏切られた。
ただし、以下の点には、「中華ファンタジー創作資料・副読本」として一定の価値を感じた。
・具体的なレシピや献立までは言及がなかったとはいえ、満漢全席の料理のカラー写真があったこと。
・第二章「材」では、ともすれば「ゲテモノ食い」にもなる、貴重・珍妙な食材解説が詳しいこと(なお、白黒写真のため価値は半減)。この箇所は、大金持ちの食事場面、それも品格、格式、優雅さを感じさせるものより、悪役金持ちの下品な宴会の参考になるでは? 中には、オオサンショウウオ(69、70ページ)やカブトガニ(82ページ)といった、日本では天然記念物に指定されているものまであった(なお両方とも、著者は「中国で食した」とのこと。当該ページで「養殖」について触れられていた)。
・本書は実質、「料理人自伝」。なので、料理人キャラ創作の参考資料になる。それも、大々的に店を開いたオーナーシェフというよりは、後述の通り、著者の店が「メニューやレシピを持たず、その時の食材と客の要望で料理を出す」スタイルのため、貴族や大金持ちのお抱え料理人や、大規模な宴席が行われるときだけ雇われる「食通たちから引く手あまたの売れっ子のフリー料理人」といったキャラ作りに役立ちそうである。また、著者の生い立ちから修行時代に関しては、自身の体験を自分の言葉で書いているので、料理人の修行や、人間関係はじめ厨房内の雰囲気をつかむことができる。
期待と現実の乖離
本書の実態は、「中華料理人・石橋幸氏の自伝」としての側面が非常に強く、私が知りたかった歴史上の食事、食の哲学の「具体的な中身」は抽象的・概念的な記述に終始していた。
皇帝食、歴史的宴席を再現したと思われる献立表の扱い
中華料理人である著者(石橋幸氏)と、満漢全席の研究にも携わった監修者(南條竹則氏)という専門的な経歴を持つことから、献立表の詳細な解説や、それに基づく料理の再現・調理法に関する深い考察を強く期待していた。
しかし、本書には、「杭州の宴席献立表」(28ページ)、「則天武后の宴席献立表」(29ページ)、「曲阜、孔子78代目子孫による皇帝料理献立表」(30ページ)、「2005年、杭州・皇帝料理の献立表」(31ページ)、「2003年、上海・大唐盛宴献立表」(155ページー160ページのページ番号不記載の箇所)といった非常に興味をそそる、歴史的宴席を再現したと思われる献立表がカラー写真で掲載されている。にもかかわらず、その詳細な解説や料理の再現・調理法に関する記述が一切なかった。また、本文中に原文引用や翻訳文の掲載もなかった。
満漢全席の対談に関する不満
中国宮廷料理の最高峰である満漢全席を取り上げた「第六章 満漢全席の記憶ー対談 南條竹則×石橋幸」は、私にとって本書を購入した最大の目的であった。だが、本書の著者略歴に「南條竹則氏とともに、2003年より満漢全席を研究」とあるにもかかわらず、その貴重な経験に基づく話題が極めて少なかった。
さらに、満漢全席再現の経験を基に執筆されたとのことで、本来であれば当該箇所を引用してしかるべき南條氏の小説『満漢全席』『寿宴』からの引用もなく、満漢全席に関する話題を事実上、これら小説を読むことへと丸投げしているかのような編集姿勢にも、大きな問題を感じた。
満漢全席再現が中国で大きく報道され、中国の料理人が大勢見学に来たという事実や、「(とても食べられない量だと思うが)12時間をかけて108品もの料理を食べられた」「それでも翌日にはちゃんと空腹感を覚えた(健康を害するものではなかった)」(160ページ)など、実際に再現した者でなければ語れない貴重な知見の部分(第六章の構成は体感的に、満漢全席が1/4、中国の食の歴史が1/4と半数程度のページを占めてはいたが)が、後半の「日本下げ」「日本落とし」の強い論調によって完全に吹き飛ばされてしまったことは、読者として非常に残念であった。
これを料理に例えると、前半は薄味ながらもそれなりの味があったにもかかわらず、後半で著者石橋氏が嫌う極端に濃い味付けの料理を出すようなものではないか? あまりにも濃い味付けのため、料理全体を賞味する舌を、料理人自らがマヒさせてしまったものではないか?
※2025年11月7日追記(南條氏作の小説『満漢全席』『寿宴』の入手性)
南條竹則氏の小説『満漢全席』(1998年集英社文庫刊)、『寿宴』(2002年講談社刊)は、追記日時点で楽天ブックスで検索したところ、両方とも「ご注文できない商品」(事実上の絶版)になっていた。刊行から20年以上経過し、『皇帝食』刊行時点において、入手性が極めて悪い(読むとなると、古本を探すか、図書館で借りるしかない)と推測される小説に、『皇帝食』最大の魅力である「満漢全席の話題」を、当該箇所の引用すらせず、丸投げしていることは、なお問題である。丸投げをするのであれば、欲を言えば、対談時には編集者とみられる進行役が同席していたのだから、その場で作者の南條氏に対し、『満漢全席』『寿宴』の『皇帝食』への全文収録許可を求めてほしかった。
特に、「丸投げ」と感じたのは以下の引用文の箇所である。引用者にて太字化した箇所は、( )でくくられていることから、文脈的に著者石橋氏、監修者にして対談相手の南條氏が書いたり発言したりしたものではなく、編集部による注記と思われる。入手性が極めて悪い他の書籍に、満漢全席の肝心な話題を丸投げした編集部の姿勢・見識は甚大である。
第六章冒頭の南條氏の紹介(154ページ)
(その成立の過程と実際は氏の小説『満漢全席』『寿宴』に詳しい)
第六章の対談168ページでの南條氏の発言の後に
(このあたりは南條氏の小説『満漢全席』をご参照のこと)
具体的なレシピの欠如
著者の店がメニューやレシピを持たず、その時の食材と客の要望に応じて料理を提供するスタイルであることは理解できる。だが、薬膳料理など、「生命の料理」と銘打つからには、その哲学を裏付ける具体的な献立例やレシピが一切示されなかった点も、読者としては物足りなさを感じた。
なお、著者はNHKの料理番組に講師として出演した際、レシピを提供できず、NHKを困らせたエピソードを記している。
でも、私の料理にはレシピがない。(102ページ)(太字・朱字化引用者)
対談における偏向的論調と主張への批判的検証 — 日本の食文化に対する論調の偏向と、その背景にある「中華思想」 —
本稿は、対談内容に対し批判的に検証を行うものである。だが私自身、南條竹則氏の著書『中国文人食物語』(中公文庫)を中華風ファンタジー小説執筆時に参考にさせていただいた経緯があり、氏の造詣の深さには敬意を表する。
本書全体、特に第六章の対談に強く感じられたのは、「現代の日本人の食生活批判」「日本の経済低迷」「昔は良かった」といった、現代日本に対する強いネガティブな論調であった。そして、南條氏、石橋氏、編集部に見られる、中国を絶対的に正しく、日本を劣った国と見なすかのような「中華思想」的な姿勢にも、中華の文化や歴史に関心があり、中華風ファンタジー好きであり、曲がりなりにも中華風ファンジー小説を執筆した私でも強い違和感と嫌悪感を覚えた。
第六章の対談において、「特に日本では、食についての意識が低かったように感じられるのですが、これはどうしてでしょう?」という編集部による唐突にも思える誘導的な問いかけ(太字引用者)から、日本を「食意識が低い」国とする論調に話が展開しているように感じられた。
「満漢全席の対談に関する不満」の項でも述べたが、体感的には「第六章 満漢全席の記憶ー対談 南條竹則×石橋幸」は、体感的には「満漢全席」「中国の食の歴史」の話題が少なくとも半数程度は占めていた。だが、編集部の唐突なこの問いと、南條氏の「武士が悪いんですよ! 」(太字引用者)のひと言によって、本書購入の最大の目的である「満漢全席」「中国の食の歴史」の話題がほとんど頭に入らず、本書全体の印象が「中国上げ、日本下げ」に決定された。
編集部は、「日本人の食意識」へ話題をふらず、実質絶版な南條氏の小説『満漢全席』『寿宴』に丸投げせず、この対談の場で満漢全席と中国の食の歴史を掘り下げるべきだった。
※本項は長くなり過ぎましたので、分離しました。全文は下記リンク先をご覧ください。
「理想」と「現実」の間の視点不足
著者が農薬や化学調味料、食品添加物に対して否定的な立場を取るのは理解できるし、自らできる限りを使わないよう努力している姿勢も読み取れる。しかし、だからこそ、「誰もが、無理なく、できる範囲でより良い食生活を営むにはどうすれば良いか?」という、読者の日常に寄り添った視点にもっと立ってほしかった。
本書の主張は一理あるものの、「理想ばかり高い」という印象を拭えない。また、著者は「健康情報」を発信しているにもかかわらず、専門書や論文、統計データの引用が一切なく、単に「好み」で語っているように映ってしまった点も、その妥当性に疑問を感じざるを得なかった。
また、「今の日本人は体に悪い物ばかり食べている」との主張は、日本人の平均寿命が伸びているという現実と矛盾している。具体的に、1970年(昭和45年)時点の平均寿命が男性70.17年、女性75.58年であったのに対し、2024年(令和6年)時点では男性81.09年、女性87.13年となっており、この半世紀で男女ともに約11〜12年延びている(出典:厚生労働省「簡易生命表」、習志野市公開資料など)。
さらに、著者石橋氏は、下記引用の発言の通り、自身の両親や兄弟を早くに亡くした原因を食に求めている。この発言により、「農薬、化学調味料、食品添加物がないため、昔の日本人が健康的な食生活を送っていた」という前提自体が崩れてしまうという強い矛盾も感じた。特に、氏の母がトコロテンが好物で、父が漁師でしょっぱいもの好きだったという具体的な食習慣の発言は、昔ながらの食が高塩分食であったなど、必ずしも現代的な健康基準を満たしていなかった可能性を示唆する。
石橋 うちの親も、兄弟も、早死になんです。それを見ていると、やっぱり食べものじゃないかなと。(第六章の対談、188ページ。太字朱字化引用者)
なお、「対談における偏向的論調と主張への批判的検証 — 日本の食文化に対する論調の偏向と、その背景にある「中華思想」 —」の項で述べた通り、第六章の対談を170ページで終えていれば、それに伴って、上記の発言は自然消滅していた。
結論
書名が示す「皇帝食」の具体的な内容ではなく、著者の食に対するストイックな思想や自伝に関心が向く読者には価値があるかもしれないが、歴史的・文化的な「食」の探求や、満漢全席の具体的な知識を求めている読者にとっては、期待外れに終わる可能性が高い。したがって、本書は「中華料理人・石橋幸の自伝」であることを、書名や帯の時点で強調すべきであった。
(2025年11月10日-13日大幅改定)