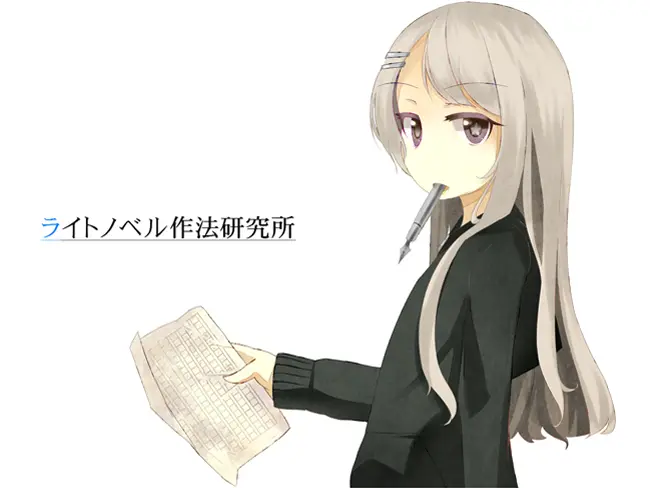『中国の服飾史入門 古代から近現代まで』
劉永華著
古田 真一、栗城 延江監訳
マール社
【総評】
128ページと薄い本ながらも、副題通り古代~現代までの中国の服飾史について一通りのことを知ることができる。また、衣裳・アクセサリーともに男女の偏りがなく、図版もオールカラーで解説とのリンクもしやすい。
【残念な点】
・清以前の服装は、上流階級中心なため、庶民の服装はほとんど取り上げられていない。
・TPO、身分別、季節ごとの生地の別の装いは書かれていない。
・満洲族の王朝の清代の衣裳を除くと、対象地域がほぼ「万里の長城の内側」。現代のものでも良いので、中国の少数民族の衣裳も一通り取り上げてほしかった。
『古代中国服飾図鑑ー唐代ー 』
左丘萌、末春著
黒田 幸宏訳
翔泳社
【総評】
Xで、「日本の中華ファンタジーの質を1、2段上げる本」とのポストが流れてきたので購入。唐代上流階級女性の服飾解説が詳しく、図版が素晴らしい。唐代の図画、像、アクセサリー現物及び再現画をオールカラーで多数載っている。また、髪型や化粧も詳細(特に額に描く模様の名称が書いてあるのが大きい)。なので、一級の作画資料である。
特筆すべき点として、「特別編」として皇族女性の婚礼衣装特集ページがあること(ただ、「唐代」に限定した本なのに、なぜか北宋6代皇帝神宗の皇后座像画が載っている)。
【残念な点】
・対象が「唐代の上流階級の女性」と、極めて限定されている。庶民女性や男性は対象外。そのぶん、妃や姫、貴族夫人などの「唐代の上流階級の女性」の服飾には非常に詳しい。「後宮ファンタジー」なら、妃や姫といった「主人」の服飾の参考には大変役立つが、侍女や下女の服飾の参考にはほぼならない(ごくわずかに侍女のイラストはあったが)。
・衣装とアクセサリーの前半部分は、解説が細かすぎるのか、本文と図版とがうまくリンクしての理解しにくかった。中国人向けに書かれた本の翻訳のためか、日本人が日本人向けに書いた本よりは、スッと入ってきづらいのでは?
・化粧・髪型はまだ分かりやすかったが、衣裳の種類、部位ごとの名称が分かりづらい。本文中に書いてはあるが、それを見付け出しにくい。一応、巻末に「着こなし方」として、衣裳の種類ごとの線画があった。だが、解説と衣裳の名称にふりがながなかった。この「着こなし方」では不十分。より拡張して、シャツ、ジャケットなど「洋服のどの種類に当たるのか」と対比した、「服飾用語一覧」を付けてほしかった。例えるなら、「登場人物名が覚えづらいのに、登場人物一覧がない小説」といった感じである。
・「フォーマル」「カジュアル」とよく出てくるわりには、TPO、身分、季節ごとの装い、生地の違いは非常に薄い。もっと詳しく書いてほしかった。
・漢民族系の衣裳が主体であること。唐代は遊牧民系の衣装「胡服」と流行したと聞いていたが、扱いが少ない。胡服など、異民族系の衣裳ももっと取り上げてほしかった。
・「セレブ」との語が頻出するのが、文体・内容的に合わず、鼻につく。
『中国明朝の服飾と生活』
陸 楚翬 著
古田 真一、栗城 延江訳
マール社
【総評】
中華ファンタジー好き、まがりなりにも中華ファンタジー小説を執筆した者としては、この系統の中国服飾史本を待っていた!
本トピックで紹介した中国服飾史本は、いずれも「だれが(身分や官職など)」「どのような場合に」「何を着る」といったTPOや、夏・冬の素材の違いの視点は極めて薄く、非常に不満だった。
だが、本書はカバーに以下のようにあるように、官位を買った富豪の地方官僚夫妻の「お呼ばれ服」、つまり他家への訪問、宴席、葬儀、婚礼、季節の儀式、正月の宮中儀式の服装(アクセサリーを含む)を、カラー図版を多用し、どのような衣裳があり、どのようなマナーで着用したかを詳述してある。さらには、これらの社交上儀礼、儀式のしきたりのフローチャートまである。
また、他の中国服飾史本では扱いが薄い、夏服・冬服の違い、普段着や下着、下着姿からの「着衣順序図」もある。そして一応、皇后の肖像画、宦官・錦衣衛(近衛部隊)の服装解説も簡単だがある。
官僚と、その妻の生活を衣裳から詳しく知ることができる極めて貴重な一冊。また、男性文人のファッションや考え方にも1章割いてある。
中華モノの創作なら必読級の一冊。リンク先の出版社のページをご確認いただきたい。一部のページが公開されている。
もし明朝の結婚パーティやお葬式に招かれたら、どんな格好で行けばよいでしょう?
本書では、中国の明朝(1368〜1644年)における性別・年齢・身分・季節による服飾の違いや、日常生活や冠婚葬祭など、具体的なシチュエーションに応じた装いを紹介。再現イラストと豊富な資料で、当時の人々の生活を身近に感じられる新機軸の図版資料集です。
貴重な装束の現存史料や模式図、当時の人々の姿を描いた絵画作品なども満載。龍や麒麟、草花などを織り表した鮮やかな文様、染色や刺繍、繊細な彫金など、技巧を凝らした服飾品の写真も見どころのひとつです。中国の季節行事や風習についても触れ、伝統や規則を重んじる当時の人々の様子を垣間見ることができます。
【残念な点】
・本書は「地方官僚夫妻」を主としているため、以下の人々の服装を調べるのには向かない。記述がないか、あってもごく簡単なものにとどまっている。
妓女、踊り子、役者など芸能関係。
日雇い労働者、職人、屋台や行商などの小商人、飲食店関係、農民などの一般庶民(「庶民の商人の妻」の衣裳は詳しく書いてあったが、主人公家出入りの相当裕福な商人。本書の「庶民」は、「官位を持たない者、文人でない者」程度であり、「経済的非富裕層」ではない)。
皇帝(皇后や高官夫人の肖像画は数多いが、皇帝について解説したページが見当たらなかった)、皇族、後宮の妃、侍女、下女。
僧侶・道士など宗教関係。
将軍や兵士の詳細な軍装(錦衣衛の服装は儀仗部隊や犯罪捜査の私服刑事の面が強い)、武術家。
モンゴル、チベット、ウイグル、ミャオなどの中国の少数民族。
・衣裳の名称が分からないストレスはなかったが、線画付で衣裳の名称や官位に応じて着用する色やアクセサリーを「用語集」としてまとめてほしかった。また、より詳細な事項索引があればありがたかった。
【付言】
繰り返しになるが、他の中国服飾史本では「○○という衣裳がある」という書き方で、着用場面については薄いことが多かった。なので、中国史なら清・宋・唐・漢・秦、モンゴル、チベット、ウイグル、カザフ、ミャオなどの中国少数民族、ペルシャ、トルコ、モロッコ、古代エジプト、マヤやアステカなどの他国もこの系統の服飾史本を読みたい。
また、明代も「地方官僚夫妻」に絞っていたので、「一般庶民編」「宮中編」「芸能編」も出してほしい。
それにしても、主人公夫妻は「男主人」「女主人」で「名無し」なのに、モブキャラは姓だけとはいえ、名前を持っていたのは何なんだ?
(番外)『中国生活図譜』
相田洋著
集広舎
「中国服飾史」に限定された本ではないが、中国服飾史本を読む際に役立つので、番外的にご紹介。上記の本は「翻訳書」であるためか、内容がスッと入ってこないこともある。本書は「日本人」が「日本語で書いた」ので、スッと入ってくることが大きい。
シリーズ名が「清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む」なので、清代の服装しか取り上げていないと思いきや、明代以前の漢服(漢族の伝統衣装)にも、庶民の普段着を中心に基礎的なことが一通り取り上げられている。ページ数では中国服飾史本のほうが上。だが、ジャケット、ベスト、シャツ、ズボン、スカートに当たる衣の種類、衿の種類と、その漢語の名前が分かりやすい。さらに、帽子、靴、清代男女の髪型、女性の下着、衣の素材(意外と中国服飾史本では衣の素材は記述が薄い)も書いてある。
なお、本書のより詳細なレビューは下記リンクをご参照のこと。

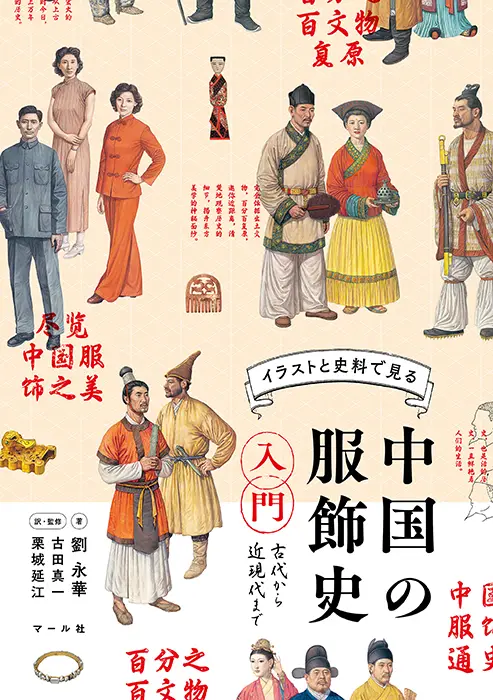
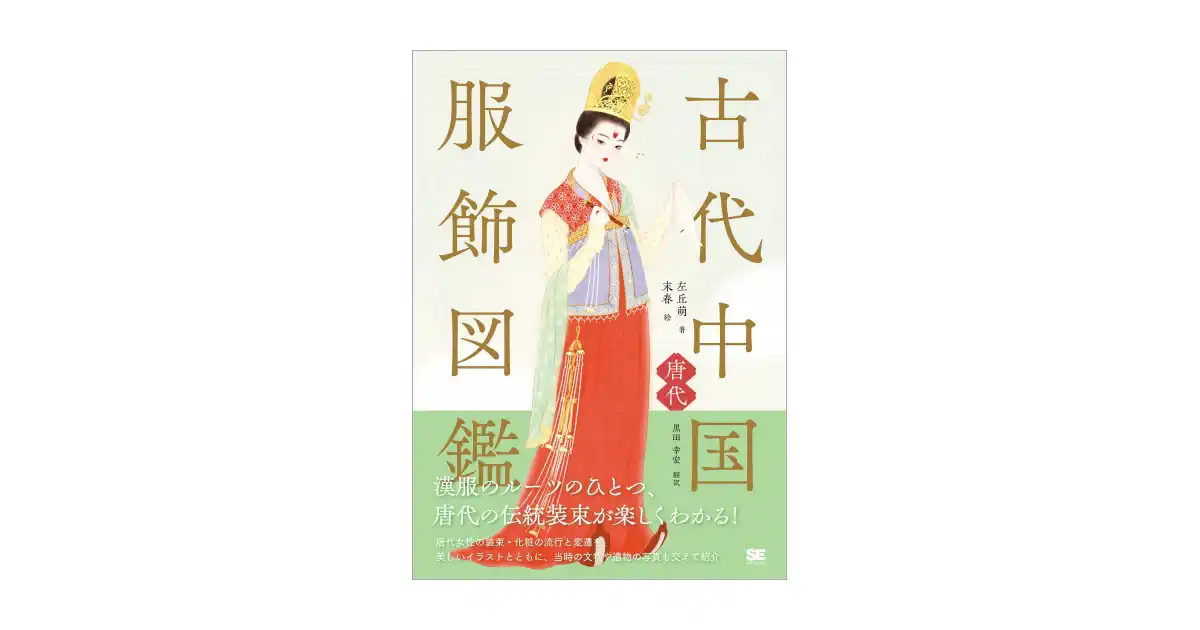


 集広舎
集広舎