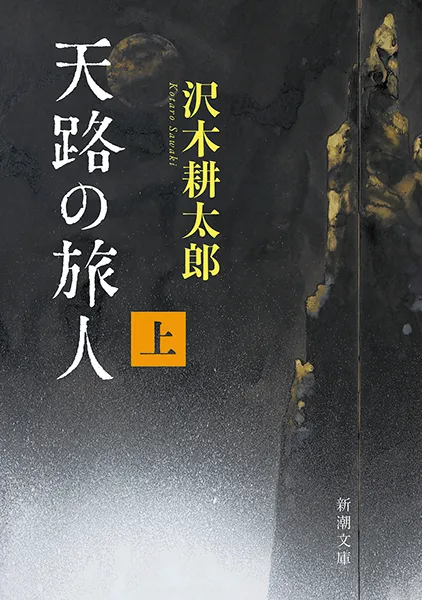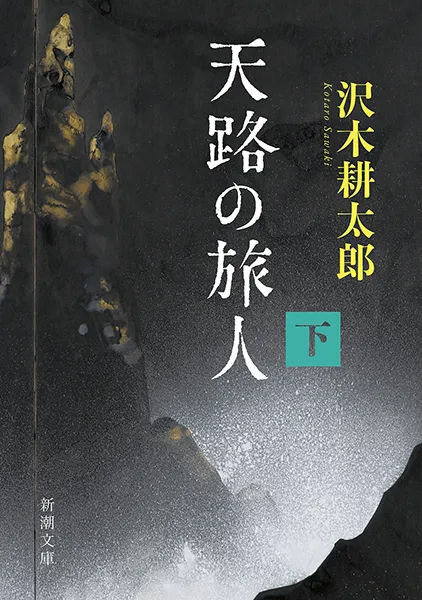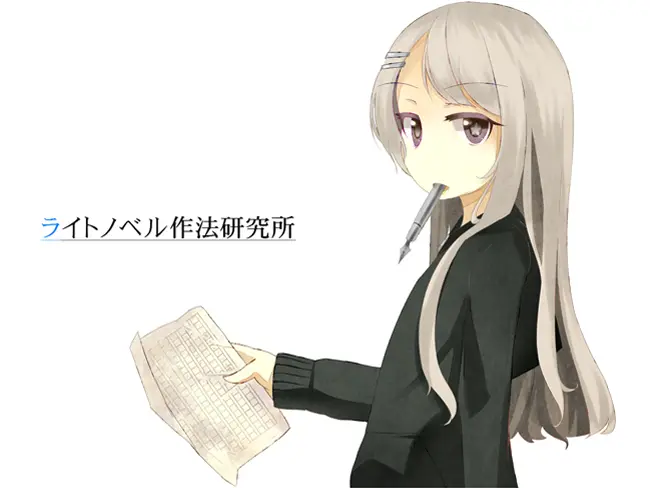『天路の旅人 上・下』
沢木耕太郎著
新潮文庫
※2025年4月23日発売予定
レビュー
※本レビューは、上記リンク先の文庫版でなく、2022年10月25日発行の単行本版によるので、ご注意。
「砂漠・荒野・高地を行くキャラバン、巡礼者、密偵(スパイ)を知るには格好の一冊」
自ら志願した日本軍密偵として、モンゴル族チベット仏教僧侶にふんして、現在の中国チベット自治区に潜入して、最後には「本物の巡礼僧」になった西村一三(かずみ)氏の手記『秘境西域八年の潜行』(中公文庫。電子版はあるようだが、紙版は入手困難)の解説書兼、西村氏の評伝。
本書の著者沢木氏は、西村氏と1年にわたり対話を重ね(西村氏は2008年没)、『秘境西域八年の潜行』の芙蓉書房版、中公文庫版、そして生原稿(廃棄されるはずだったが、担当編集者が廃棄をためらい個人的に保管していた)を丹念に読み込んで、再構成している。
1945年(昭和20年)前後の、中国内モンゴル自治区、青海省、チベット自治区、インド方面の貴重な見聞記でもある。
創作の資料とて役立つのは以下の通り。
1、キャラバンのパーティー構成、1日の移動距離。西村氏は、案外単独行動をしていない。特にチベット到達前までは、キャラバン(隊商)を組織したり、混ぜてもらったりしている。人家が少ない(下手すると数カ月単位で家を見ない)砂漠や荒野の単独行は自殺行為。
2、旅での移動方法、食事、宿。
3、旅での装備品。
4、無一文で巡礼して、喜捨を得る方法。また、人々はなぜ巡礼者に喜捨をするのか?
5、日本人だとバレると、命の保障がないないなか、身分を秘匿する方法。
6、インドでは鉄道を利用しているが、旅の前半は徒歩やラクダ、ヤクなどの家畜に頼る前近代の旅。なので、「前近代(徒歩・家畜)」と「近代(鉄道)」の旅の違い。
単行本版に限れば、料理やチベット仏教関係のモンゴル語、チベット語が覚えづらい。初出時に説明があるが、二度目以降は説明がないことが多い。日本語訳で書いておいて、初出時にモンゴル語、チベット語のルビを振るほうがよかったのでは?
本書の原典『秘境西域八年の潜行』は、膨大な記録のため省略が多く、順序の入れ替えもあり、かなり読みにくいとのこと。『秘境西域八年の潜行』の芙蓉書房版、中公文庫版、生原稿を丹念に読み込み、西川一三氏と対話を重ね、そのご夫人、ご令嬢とも親交のある沢木氏により、この『秘境西域八年の潜行』が失われた部分が可能な限り復元され、整理されて「完全版」として、再刊されることを望む。