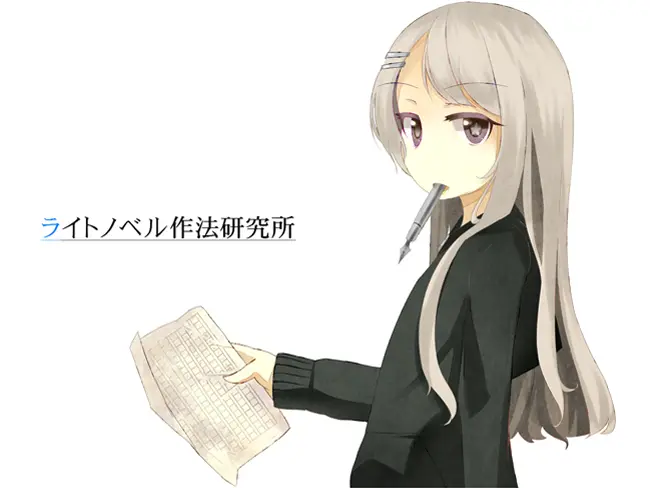トピックの字数制限の関係で「本文」「付言前編」「付言後編」の三つに分けます。「本文」「付言前編」は以下のリンクからどうぞ。
3、キリスト教、西洋近代文明の押し売り、住人のプライベート空間への侵入ではないか? との疑問
キリスト教、西洋近代文明の押し売りし、住人のプライベート空間への侵入しているのでは? との疑問も感じた。バード女史は、中国人の礼儀、道徳、文明を論じていた。私は、バード女史にこのように問いたい。
「バードさん、あなたは中国人から見て、慣習と礼儀にかない、道徳的・文明的振る舞いをしていましたか?」
すでに詳述したように、「覆いのない轎」に乗り続けるという、現地民からすると「憎悪」の対象になる行為を繰り返していた。これがどうしても疑問である。
本書は、バード女史自身による序の末尾「本書を中国と中国問題に関する世論の形成に役立つ資料作成の真摯な試みとして受け入れていただければ幸いである」と、2巻の訳者解説の「3 中国と朝鮮の旅をめぐる仮説――中国旅行記の理解と鑑賞のために」を読むと、先に読んだ『ロッキー山脈踏破行』『チベット人の中で』とは異なり、英国政府への対中政策(特に通商関係)、宣教師への対中伝道の「助言の書」では? と感じている。実際、1巻には貿易統計が付録として付いているし、四川省入りしてからも「どうすれば英国製品が受け入れられるのか?」との記述もある。そして、2巻第三十九章の章名が「中国のプロテスタント系伝道会に関する覚書」。
『ロッキー山脈踏破行 』はキリスト教国で、西洋近代文明国のアメリカが旅先なので感じなかったのは当然としても、西洋文明国のキリスト教徒からすれば「未開の地」である旅で、キリスト教伝道の記述の多い『チベット人の中で』(インドのラダック地方)でも、バード女史によるキリスト教、西洋近代文明の押し売りは特に感じなかった。『チベット人の中で』では、非キリスト教徒からも大変慕われている現地駐在の宣教師が同行していたとはいえ、橋のない増水した川を、村人総出、かつ命がけで、バード女史一行を渡してくれたことを見ても、バード女史の人徳を感じられたのだが。
だが、本書ではずいぶん印象が違う。バード女史が中国人に対して厳しい見方をするのは当然ではある。だが、2度も襲撃を受け、2度目では重傷を負わされたにもかかわらず、中国人への憎悪をあらわにしない極めて公正なバード女史をして、それが人道的善意に基づいていたとしても「未開の野蛮人は、キリスト教と西洋近代文明で教化されなければならない」との考えを持っているように感じられる。西洋近代文明国のキリスト教徒と東アジアの多神教・多宗教文化とでは、どうしても越えられぬ壁を感じ、根本の部分では相容れないものを禁じ得ない。
バード女史は、布教方法や教会の形式が外国の要素を持つことで、キリスト教が「異国の宗教」と見なされてしまうと指摘し、キリスト教精神に反しない慣習はすべて守り、キリスト教を中国の国民性を支持する形で「中国の国民生活に害とならないもの」と合体させるべきだと提言している(2巻第三十九章336~337ページ)。
上記の太字にした部分は、以下に引用する箇所との矛盾を感じる。中国の慣習が「キリスト教精神に反」する場合はどうするのか? 既存の慣習・信仰を、「迷信」として否定的に見ることは、「中国の国民性を支持」することにはならないのでは? むしろ、中国人に対する「敵意」ではないか? 中国人の祖先崇拝を、「この慣習は、子が親を思う優しく麗しい感情に発するものであろうが、明らかに主として恐怖心によって起こされてきている」とまで書いている(2巻第三十九章327ページ。太字は引用者)。このように中国の慣習を否定的に見ていて、キリスト教や西洋近代文明が真に中国人に受け入れられるのであろうか?
なおバード女史は、2巻「結論」327〜330ページで、自身のキリスト教伝道観や中国(アジア全体を含む)の宗教の問題点を、おおむね以下のように記している。
伝道活動への初期の姿勢と変化
- 8年に及ぶアジアの旅の初期(1878年の日本など)は、伝道活動にほとんど関心がなく、宣教師を鼻であしらうことさえ楽しんでいた。旅では伝道会の拠点を避けていた。
- しかし、後半の旅(1889年の小チベット<インドのラダック地方>など)で住民の悲惨な状態に胸を打たれ、キリスト教への改宗こそが状態を良くする「偉大な方法」であり、西洋人の義務であると考え直すようになった。
- 伝道会は、今や中国を目覚めさせる非常に重要な役割を果たしており、無視すべきではないと述べている。
キリスト教がもたらす「天恵」
- キリスト教がアジアの国々に伝えるべき「天恵」として、父なる神の認識、男らしさ・女らしさの理想像、政治的自由、女性の地位、公平な戒律の尊厳、そして正義を支える世論など、西洋が歴史の中で獲得してきた諸々の恩恵を挙げている。
- これらの天恵を伝えず、中国を単なる貿易相手地域としか見ないのは、キリスト教精神に反した利己主義であると強く批判している。
中国の宗教(仏教)の現状と問題点
- バード女史は、目にした宣教師の善行と、アジアの絶望的な宗教制度に心を動かされた。
- 仏教などのアジアの宗教は、当初は進んだ崇高な考えを持っていたが、何世紀にもわたる変遷の中で素晴らしさを失ってしまった。
- 中国の仏教は今や未開の国々の邪教程度のものになっている。
- 既存の鬼神信仰、自然崇拝、偶像崇拝を大いに取り込んだ結果、幼稚な偶像崇拝や妖術まがいのものがはびこっている。
- 寺院は奇怪な偶像にあふれ、僧侶は徳を失い、高潔な教えは影をひそめている。
- このような堕落を阻止する手立ては全くなく、〈アジアのどの宗教にも復興の力はない〉と断定している。
ここまで仏教寺院に否定的な見方を書いておきながら、旅の最中には中国の寺院を訪れている。そこでは「何を見たか」を感情を交えず、淡々と事実を記述していた。ここにもバード女史の言動の矛盾を感じる。
本書全巻を通してだが、「キリスト教と西洋近代文明が『知的で道徳的で正しい』」を大前提に、それを基準にして、「未開の野蛮国」を「知的か?」「礼儀正しいか?」「文明的か?」を判定しているように感じられてならなかった。バード女史は、「仏教は堕落した」と書いていたが、何をもって「堕落」と見えたのだろうか? 19世紀末時点で非キリスト教徒から見て、キリスト教が堕落してなく「清い」存在であり、今までの信仰や慣習を捨て改宗するほど魅力があるものと断定できるのか? 礼を備えて「道徳的」なものなのか? キリスト教に無知な私からすると、バード女史の宗教観はよく分からない。
訳者解説・あとがきでは、バード女史にとってキリスト教伝道が極めて重要なものと強調されていた。だが、「バード女史にとってのキリスト教伝道とは何か?」「亡き妹の名を冠した伝道病院建設の地を中国奥地に選んだ理由は?」「対外感情が極めて悪い時期になぜ中国奥地を旅したのか?」との疑問を禁じ得ない。訳者解説では、直近の朝鮮旅行を「英国政府の委託による調査活動では?」のとの仮説を立ていた。極東にいて、そのついでに足を延ばしたにしても、「ついで」の域をはるかに超えている。
バード女史にとっての伝道とは、単にキリスト教徒の数や、教会の数を増やすことではなさそうではある。伝道に対する態度は穏健なもの。だだ、それでも「キリスト教押し売り」との感があり、鼻につくが。田舎の農家に泊まった際、好奇心から地元の女性たち30人の訪問を受けた際にこう書いている。
バード女史は彼女たちの素質、気骨、親切心、慎み深さ、忠実さを高く評価し、「もしこのような女性がキリスト教徒になれば、きっと完璧なキリスト教徒になるであろう」と期待を述べるにとどめている(1巻第二十四章412ページ。太字引用者)。
バード女史は「きっと完璧なキリスト教徒になるであろう」とは書いても、「キリスト教徒にならければならない」「彼女たちをキリスト教徒にしなければならない」とまでは書いていない。また、当該箇所を読む限り、この場ではキリスト教については話題は出ていないし、バード女史が改宗を勧めることもしていない。
本書では、高らかと「○○宣教師は何人の中国人を改宗させた」「何軒の仏教寺院、孔子廟、道教寺院を破壊した」「何軒の教会を建てた」とは書いていない(少なくともそのような印象は持たなかった)。キリスト教の伝道というと、改宗者数、破壊した他宗教施設数、建設した教会数をほこるイメージがある。
博識・公正なバード女史も、「門前の小僧」どころか「牧師の娘」。キリスト教的価値観を持たぬ人は「不幸な人」「かわいそうな人」なのだろうか? バード女史が望んでいた伝道とは何か? ことごとく仏教寺院、道教寺院、孔子廟が破壊され、キリスト教会となり、中国人全てが祖先の位牌ではなく、十字架を拝むことなのか? それとも、インド以東、特に東アジア(中国・日本)の多宗教・多神教文化(日本の神仏習合)に合わせて、儒教・道教・仏教の「三教」にキリスト教が加わる「四教」になることだったのか? つまり、同一人物が儒教・道教・仏教を掛け持ち信仰する中に、キリスト教が加わることを認める姿勢なのか? 東アジアの多宗教・多神教文化では、日本の神仏習合のように、他の宗教との「掛け持ち信仰」を認める宗教でないと、定着は難しいのでは?
バード女史は2巻354~365ページの「結論」の章では、「西洋の酵母」(太字朱字化引用者)との節を設け、西洋の知識、キリスト教という夷狄(西洋人)の知識・技術が中国人の自惚れを打ち破り、中国の発展に役立つことを高らかとうたい上げている。そして、下記の通り、その事例を細々と列挙していた。
西洋技術が打ち砕いた中国の自惚れ
- 西洋が発明した機械、蒸気船、鉄道、電報、精密兵器、外科医、そして租界の美しさや際立つ富などが、これに触れた中国人の自惚れを打ち砕いてきた。
中国における西洋技術の受容
- 中国人は現在、電信線を利用し、汽艇を運航し、西洋式の病院に医学生として入学している。
- 写真も芸術的センスは欠けるが、技術的にはほぼ完璧なものを撮っている。
- 中国人が所有・経営する工場も興っており、「招商局」は揚子江下流の大きな定期客船会社の一つとなっている。
- 奥地にもたらされた生活用品の影響
- 内陸(奥地)に住む外国人が持ち込んだ灯油ランプ、石鹸、マッチ、缶詰、ミシンなどが、中国社会の生活に変革をもたらしている。
- 特に灯油ランプは社会生活の変革に大きく寄与し、ミシンは仕立て人の間に導入された。
- これらの有効性が認められたことで、中国人は「未開人」(夷狄)の能力を認めざるを得なくなった。
学術・思想面の影響(「西洋の酵母」)
- 決して軽視できない影響として、西洋の学術書、歴史書、キリスト教の書物が流布したことが挙げられる。
- これらの書物は、この国の知識指導者や指導者に影響し、中国という「粉全体を発酵させる西洋の酵母」**である。
- 皇帝が改革のための勅令を発布したことは、皇帝が以前から西洋の書物を熱心に読んでいたことに直接結びつくことに疑問の余地はない。
博識・公正なるバード女史をしても、西洋近代文明とキリスト教に関する「自惚れ」を禁じ得ない。
また、本書に持った違和感の一つ、「バード女史とはこんな人だったっけ?」は、この「西洋の酵母」の箇所と、先に間接引用した2巻第三十九章327〜330ページの部分で、ある程度理解ができた。邦訳が確認できなかったマレー半島、ペルシャ、モロッコの旅を目的に、本書以前に読んだバード女史の伝記『イザベラ・バードーー旅に生きた英国婦人』(パット・バー著、小野崎晶裕訳、講談社学術文庫)でのバード女史は、「大英帝国の『ご威光』と蒸気船・スエズ運河などの『西洋近代文明の恩恵』で旅ができているのにもかかわらず、それを毛嫌いする。そして、旅先の人々に『西洋化・近代化することなく純朴のままでいてほしい』と言う人」との印象が強かった。
本書では、キリスト教・西洋近代文明礼賛とまではいかぬものの、中国その他「未開の地」に対し、「西洋化・近代化・キリスト教化してほしい」と言う。
また「第三十八章 ケシとその利用」では、中国人のアヘン中毒を詳述し、バード女史はこのように締めくくっていた。
中国はどのようにして急速で増大しつつあるアヘン常用癖から自らを解き放つのであろうか? これは、この民族のこれまでの驚くべき活力を奪い取りつつあるのである。(2巻317ページ)
英国がアヘンを中国に持ち込み、結果的にアヘン戦争につながったことにまったく触れていないどころか、「中国におけるアヘンの栽培と利用の歴史について触れるつもりはない」と逃げ口上を打っている。一応、インド産アヘン(原著刊行当時、インドは英国領)が中国で輸入されていることには触れてはいる。だが、アヘン戦争に触れた上ならともかく、英国人がこれを言える義理はあるのか? 本旅行は、英国首相を通じて清国政府の旅行許可を取得しているので、アヘン戦争には触れることができなかったのか? 英国人のアルコール中毒には触れられているので、それほど「一方的」ではなかったが。
バード女史の伝道観、西洋文明押し売りについて、訳者には解説・あとがきでより深堀してほしかった。
本書が19世紀末の長江流域・四川省の模様を知るには超一級の史料ではある。ただ、最近の日本では、外国人旅行者による観光公害が深刻化している。その中で本書を読むと、その克明な観察・記録のために、外国人が歓迎されていないどころか、強く憎悪されている所へ行き、住民の生活を観察することは、客人のために用意されている「客間」ではなく、寝室・書斎などの「住人の極めてプライベートな空間」に押し入るものではないか? と感じてならなかった。バード女史の旅行記『ロッキー山脈踏破行』『チベット人の中で』は、日本での観光公害が深刻化する前に読んだこともあり、このような疑問は感じなかったのだが。
また、バード女史は1巻第十九章320~324ページで、町の宿における宿泊環境について激しく憤慨している。「持ち物を盗まれる」「部屋に隣室から穴を開けられて覗かれる」「宿の女房」など女性たちからの「持ち物吟味、質問攻め」という目に遭っていた。
特に、隣室から漆喰の壁を削って穴を開けられ覗かれる行為が最も腹立たしく、穴の向こうから聞こえるひそひそ話やくすくす笑いに耐えかね、その穴に連発拳銃か洗浄器の口を向けてやりたい気持ちに駆られたと述べている。この穴あけ行為は、無知な苦力(人夫)ではなく、きちんとした身なりの旅行者(知識層)の仕業であることが多かった。
さらにバード女史は、自身が着用していた「中国服、日本の笠、英国製の手袋と靴」という「ごった煮」スタイルが、女性たちにとってしゃくの種になっていたと分析している。彼女らの質問は「軽薄」で「異常なまでに知性を欠いた」好奇心に基づくものであり、大人としての異常なまでの無神経さがうかがえたと憤っている。
また、知識層(文人階層)の好奇心は「残酷で侮辱的」であり、外国人に対する敵意をかき立てる傾向があった。さらに、夜間に写真の現像を行っている最中、隣室からの壁の穴あけによって光が入り込み、貴重なネガが台無しになったことにも激しい怒りを示している。
ここまでするか!? との感じで、この憤慨はもっともではある。ただ、言葉は悪いが「珍獣(中国人)を見物しに行ったら、逆に『珍獣として見物された』」との印象も持った。また、知識層の多い都市よりもそうでない田舎、旅前半の漢族の地域よりも、旅後半のチベット人の地域のほうが、敵対性や「珍獣」扱いされる度合いが少なく、自然に接してもらいやすかったのが印象的だった。
さらに、本書が「現代の旅行系動画」とすれば、観光地でもなく、旅行者が来ることを想定していない、ごく一般的な住宅街で撮影するようなものではないか? バード女史はいわゆる「迷惑系配信者」ではない。ただ、友好的に撮影できたとしても、そのような動画が多く再生されれば、安易にマネをする配信者が出てこないか? 特に「迷惑系配信者」をおびき寄せる結果にはならないか? との懸念を持ってしまった。
本書を読んでいると、バード女史の細かな観察・記録故に、ドラえもんの透明マント・石ころ帽子を使って、他人宅に侵入し、住人の生活を「観察」している気分になった。どうにも気まずいというか、据わりが悪い感じがする。
本原著刊行当時なら、時間・費用をとっても簡単にマネできることではない。さらには、バード女史が清国政府より高官待遇の旅行許可(この旅行許可はバード女史の安全を保障することにはなっていたが、十分な機能はしていなかった。だが、この許可のおかげでケガぐらいで済んだのではないか?)を得られたのは、英国首相に伝手があってのこと(2巻第三十一章163ページ)。「迷惑配信者」がマネしたくてもマネできない状況で、それを懸念し、対策する必要がなかったことは幸いである。
バード女史は、宿坊での会話から明らかになる文人階層の無知さ加減に激しく憤慨している(1巻第十六章274、275ページ)。彼らの会話には、以下のような国際情勢や外国に関するトンチンカンで滑稽な誤解がとめどなく現れたという。
中国の文人たちが世界を知らないのに比べて、バード女史のほうが誤解が皆無ではないにしろ「中国を知っている」。
国際情勢の誤解。 清末の黒旗軍が台湾から日本人を駆逐し、その祈りの力で台湾海峡が開いた、あるいはロシア、イギリス、フランス、日本の海軍が広範囲にわたる戦禍でやられてしまった、といった話。
英国への誤解。英国女王が中国に従属しており、英国の大臣が貢ぎ物を捧げようと北京に滞在している、あるいは女王が西太后に送った誕生日の贈り物が特別な貢ぎ物だったという思い込み。
米国への誤解。アメリカの使節団が、暴動の被害査定ではなく、新しい太守の就任祝いとして派遣されたと信じていること。
外国の奇妙な描写。中国の外にはイエス・キリストという百姓上がりの皇帝が統治する五つの王国があり、そのうちの一国には犬顔族が住んでいる、また別の国では女性が二人の夫を持ち、胸の穴に棒を通して運ばれるといった奇妙な話。
- 宣教師の目的の誤解。宣教師が僻地に来て住んでいるのは、中国の偉大さの秘密を探り出し、魔術によって破壊するためだという盲信。
- 地図に対する誤解。訪問者がアジアの地図を見て、「外国の悪魔(洋鬼子)が、神をまどわすために中国を地図の上でこんなに小さくしやがった」と話すのを宣教師が立ち聞きしたという事例。
確かに文人たちの当時の国際情勢の認識が、滑稽なほどトンチンカンで笑ってしまう。ただ、トンチンカンな認識でも、外国人への危害を防ぐ意味でも「誤解」させておいたほうが良かったのでは? という気もする。その理由や背景について、十分な観察・分析がなかったのはもどかしい。また、本原著刊行当時の一般の英国人たちは、中国の文人たちを笑えるほど「中国を知って」いたのだろうか?
『中国奥地紀行』(全2巻)
イザベラ・バード著
金坂清則訳
平凡社ライブラリー