読んでない、読んでない。(笑) 昔、大学の図書館やスポーツクラブにおいてあった時には、ただだから読んでいたが、自宅で取るには高過ぎる。 以前は、ヘラルドトリビューンが月5000円くらいだった気がするが、それがこれまでの最高値購読料かな。 フェイスブックの投稿からコピペしただけ。
FT読んでるの。すごいな~ 飛行機に乗る時他に選択肢がないと手にする事もあるが、大抵一面をチラ見して終わり。 4週間100円でその後9千円/月というのにややびびった。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
ホントだ、黒海ヨーグルトと言うべきだ。 ジョージアと言うのは、いまいちマイナーな地名なので、カスピ海を使ったのかもしれないと思った。 地球温暖化が進めば、この地域のヨーグルトもすぐに腐るようにならないか心配。 下のサイトを見ると、南欧では段々とワインの原料の栽培が出来なくなり、デンマークやロシアで栽培可能となるらしい。
https://www.ft.com/content/1c94c23a-90f1-465f-99c0-0c83f9b20b49?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1NhJLVjNpr2q9-DX4CLk9JcpeNZykAMo5-2zNYimwamY0Ul5XGihEjsmU_aem_pX37PxyImO-wEU_vcUgC9A
カスピ海ヨーグルトの起源はジョージア https://www.caspia.jp/cywhat/roots/
ジョージアはカスピ海ではなく黒海に面しているので、黒海ヨーグルトと呼ぶのが正しい。黒はヨーグルトのイメージに合わず、地中海は遠すぎるのでカスピ海としたのか。グルジアヨーグルトでもよかったのだろうが、ブルガリアと被るので止めたのだろう。
コーカサスヨーグルトがそのまんまで分かり易いと思うのだが、ケフィア(=ヨーグルトきのこ)との混同を避けたか。
Tanti auguri di buon Anno!
そう言えば、カスピ海ヨーグルトの宣伝にコーカサス地方原産との説明があった気がする。 昔、バリ島で日本人の旅行者だけが良く腹をくだすと言われていたが、私は何度言っても大丈夫だった。 歯を磨くときにミネラルウォーターを使わなかったが、水道水はとても飲める代物ではなかった。シャワーの水も、海水を薄めたものを浴びているようだったし。 !Feliz Año Nuevo!
ジョージアのバツーミのビーチでは海水を飲まないよう気を付けよう。 カスピ海ヨーグルトの菌はカスピ海の水で培養されている訳でもなく、コーカサス地方原産という意味だから問題ないと思うけど。コーカサスや中央アジアでも基本気にせず飲み食いする予定。 ところで中央アジアに行くとたいていの日本人はお腹をやられ、理由は水ではないかとされている。歯を磨くの迄ミネラルウォーターを使ったのにやられたという話もある。恐らく料理に大量に使われる綿花油の消化酵素が少ないせいだと思う。
ジミー・カーター大統領は共和党の人間からも、その人間性は高く評価され the Great Manと言われているようである。
ロシアや中国に接する内海は何が流れ込んでいるか、全く信用ならない。放射能など垂れ流しの可能性もある。 以前、原子力に詳しい教授から聞いたのだが、福島から海に流れる放射能など、太平洋で拡散されて無視されるレベルだが、中国や北朝鮮の核実験で出る放射能は陸続きなので、韓国や香港の水でさえ放射能が混入しているはずだとのこと。 カスピ海ヨーグルトなどと宣伝している商品もあるが、とても買うつもりにならない。
EuropeのビーチリゾートへはLCCやチャーター便が頻繁に飛んでいるので、陸路の接続はそれ程問題にならない。黒海沿岸のリゾートがぱっとしない理由は、昔から安かろう。。。のイメージがあるのと、黒海の水質が地中海程綺麗ではない事。後者については断定はできないが、ウクライナ、ロシアから流れ込む河川の汚染に起因しているように思う。
>> 9086 そう言えば、カーター大統領は、退任後、選挙監視団を途上国に送る等のボランティア活動をしていたが、ブッシュとゴアの大統領選挙がもめたときに、自分の国の選挙に嫌気がさすとともに、恥の意識が芽生え、もう選挙監視ボランティアをしたくないと言ったのを覚えている。 最近でも米国は似たようなことがあったから、晩年、カーター大統領はどんな思いでいらしたであろうかと思ってしまう。
>> 9084 やはり、欧米から高速鉄道や高速道路でのアクセスが良くないと、リゾート地も垢抜けないのかもしれないのかな。 ちょうどさっきまでテレビで、日本の職人が、ギリシア、ルーマニア、ブルガリアの田舎町に行き、建物等の修繕をするという番組をやっていた。日本と違い、湿気が少ないからであろう、粗末な造りの家が多い印象だった。
カーター大統領は、在職中よりも元大統領としての功績が大きいことで有名。その功績でノーベル平和賞も受賞している。 英国はどうだか知らんが、米国大統領は、大統領を辞めた後、その立場を活かし、様々な活動に勤しむのが普通。オバマみたいに院政を敷して現職に影響を及ぼそうなんて、日本の元首相がやるようなセコイことをするのは例外の部類に入る。トランプ次期大統領もこの4年間、そのけがあったが、再選を目指していたということで別枠。 日本では、明治時代にグラント元大統領が来日したが、これも元大統領として清国と日本の仲介をしたり、明治天皇に様々な御進講をして、感謝されている。
ケネディ大統領は、若くして大統領になったので、大統領在任中のインタビューにて大統領退任後は、上院議員になって国に奉仕したいと答えている。 話をカーター大統領に戻すと、元大統領として、「キャンプ・デービッド合意」の仲介、金日成主席と会談し「米朝枠組み合意」の足掛かりを築いたり、カーターセンターを通じた様々な人権活動をするなど、元大統領としての活動は、傑出している。
He should have become ex-President without becoming President. と言われたくらいだ。
旅行がファーストクラスと五つ星ホテルの利用であることは疑いないが、それ以上に家族を含めた終身のシークレットサービスと年金にお金がかかる。これも最近、改正されて縮小されたか、される予定らしい。 なお、カーター大統領は、在職中に歳費をもらっていたが、ケネディ大統領とトランプ大統領は、在職中に歳費すらもらっていないらしい。(正確には、年収1ドルとかにしている。)
ジミー・カーターって印象が薄いと思ったら大統領の任期が77-81年とは、びっくり。トニーブレアとかもそうだけど若くして首相や大統領になった人は辞めた後何をしているのかが気になる。文化活動という名目でファーストクラスの世界旅行、高級ホテル滞在、グルメ三昧か。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
クロアチアの地中海沿岸はawesomeだね。しかし内陸に車で5キロも入るとgenuineになってくる。昨今モンテネグロはもちろんアルバニアのビーチも随分と垢ぬけてきたらしい。山道なのにガードレールがなくて見た目おっかないのは直ったかな? ルーマニアやブルガリアのビーチにはもう長い間行ってないが、庶民的な雰囲気は余り変わっていない気がする。
来年夏のシルクロート旅行でトルコからジョージアへ黒海に沿って移動する予定なので、状況報告ができると思う。
バルカン諸国とバルカン半島の国とは違うのか。 Wikipediaをみたら、次のような記述があった。
『1991年6月から始まったユーゴスラヴィア崩壊の後、「バルカン」という用語は(特にクロアチアとスロヴェニアにおいて)ネガティブな政治的意味合いを持つようになり、世界的にも武力衝突と領土の断片化を指して自然に使用されるようになった(バルカニゼーションを参照)』
クロアチアは、旅行した人が綺麗な街だと言っていたので、awesomeなんだろう。 前述の地図には黒海沿岸がawesome areaに含まれていないなあ。世俗的には、まずエーゲ海を見てからにしろ、ということか。ナポリやソレントで地中海を眺めた時、一日中、ホテルの部屋から海を眺めていてもいいと思ったが、エーゲ海や黒海は、さらに異なる趣きが楽しめるのだと思っている。
所謂『バルカン』地域ね。バルカン半島にはギリシャやトルコのヨーロッパ側も含まれるが、『バルカン』地域には含まれない点に注意。スロベニア人やクロアチア人もこぞって自国は『バルカンに含まれない』と主張するだろう。そうなるとボスニア・ヘルツェコビナ、セルビア、モンテネグロ、コソボ、アルバニア、ブルガリアか。"awesome"は褒めすぎで、よく言って"genuine"くらいだと思う。
個人的にはルーマニア、ブルガリアの黒海沿岸が気に入っている。昭和の海水浴場を想い出させるという点で。ビーチリゾートならバルカンではないが、トルコのアンタルヤかギリシャのロードス島がいい。
カーター大統領が亡くなった。米国では、大統領経験者は大統領職を退いてからも、President 〇〇 と呼ぶことが多い。 アトランタにあるカーターセンターを訪れた時、立派な日本庭園があったのを覚えている。うちにも遊びに来たスペイン人がどういう経緯か、カーターセンターでスペインの料理をペラペラと紹介していたら、カーターセンターの料理を手伝うことになったということもあったっけ。 カーター大統領は、日本を訪れた初めての現職大統領で、昔、東海道線で東京からペリー来航の下田まで移動するので、線路沿いにものすごい数の警察官が配置されていたのを覚えている。 R.I.P.
>> 9078 アメリカ人の見ているヨーロッパは、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツくらいで ヨーロッパ人の見るアメリカは、New Yorkとロサンゼルスだけだというジョークがあるが グリーンガイドみたいなマーケット戦略に忠実であろう会社は、売れるところに絞っているのかもしれない。何しろ、ミシュラン発行なんだから。
東欧こそ、商業主義に毒されたツーリズム抜きに楽しめる真の旅行先との書き込みが、フェイスブックにあった。私も毒された一人ではあるが。 先日、紹介してくれた『異国の窓から』を先程、読み終わった。ドナウ川への憧憬とソ連時代の東欧のギスギスした雰囲気を上手く描写している紀行小説だ。 最後のローマのくだりは、自分が訪れた時を思い浮かべながら読めたが、東欧は未開拓なので、想像力を膨らませ堪能させていただきました。
失礼、正しくは、Roman Question でした。英語は、ラテン語からの訳語らしい。 日本訳のローマ問題に引かれて、間違えて記憶した。初めて読んだのは、グリーンガイドの英語版だったのだが。
ラテラノ条約によって解決したのは、ムッソリーニの偉業の一つ。 ムッソリーニは、ヴァチカンを認めるとか、マフィアの掃討とか、経済対策を含め、色々といいことをしたが、組んだ相手が悪かった。ヒトラーが見せたドイツ軍の一糸乱れぬ行進を見て、コレダ! と思ったらしい。 他方、フランコ将軍もヒトラーと一緒に戦うように延々と説得されたそうだが、ヒトラーを子ども扱いし、相手にしなかったとの記録が残っている。これを見ていた元ドイツ軍の関係者が言うには、役者が違うということだったらしい。 人間の器と言うのがリーダーの論評をするときなどに、よく言われるが、こういう時に露わになるのであろう。そして国全体の運命を決めてしまうのかもしれない。 フランコ将軍は、国民から選ばれておらず、ヒトラーとムッソリーニは、形式的には国民から選ばれているので、スペイン人は運が良く、ドイツ国民とイタリア国民は、自ら蒔いた種と言うことなのかもしれないが。
今は亡き書籍版のフライトプランナーや、LPを買いによく銀座の丸善迄行ったけど、Michelin Green Guideって手に取った事すらなかった。理由は旅行テリトリーだった東欧、旧ソ連やアラブ編が出版されていなかったから。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
Roman problem って何? 「I love Roma ❤」と書かれたTシャツを見て、びっくりする事ではないよね。
>> 9075 昔、書店で色々と見比べた時にLonely Planet も見たと思うが、確かMichelin Green Guideを買った。 日本で買ったか、アメリカで買ったかは覚えていない。 このグリーンガイドは、初めのぺ数ページが観光地の歴史を結構なボリュームで説明している。ローマの場合、Roman Problemのことも日本の教科書にはないのに、丁寧に説明されていて驚いた覚えがある。ちなみに先日、アメリカ人に聞いたら、アメリカの高校の教科書でもRoman Problemは出てこないだろうとのこと。ただ、大抵のインテリのアメリカ人は知っている。 最近は、欧州でも米国でも友人の家に泊まり歩き、無銭飲食を繰り返すのと、観光地に対する興味が薄れてきたので、ガイドブックを持ち歩かずに現地で適当に情報を集めたり、ネットで見て情報収集は終わりにする。そもそも、友人が案内してくれるし。
Let's goシリーズは読んでいたが、Lonely Planetの網羅性には敵わなかった。実際前者はパンデミックで廃刊に追い込まれたが後者は現存。ネットでかなりの情報を得られるようになった昨今、LPも営業的には苦戦はしていると思う。Iran, Turkey, Centra Asia編のLPをダウンロードして旅行の準備に読んでいるが、以前のように旅行に必須という感じではなくなった。 地球の歩き方中央アジア編の新刊が先月発売され早速ダウンロードしてみたが、ちらっと見て内容が薄いのを確認して以来開いていない。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
コソボと言うのは、「セルビア建国の地」と言われているが、住民の9割はアルバニア人。 セルビアとモンテネグロは、Wikipediaによると言語的、文化的には違いがないそうだが、コソボ紛争は、セルビア人とアルバニア人のゲリラとの戦いから始まったらしい? それでもって、アルバニア人には、アルバニアと言う国が別に存在する。 そこに北マケドニアと言う国があるが、ブルガリア人は、マケドニアはブルガリアの一部だと思っているらしいし、第一、来たマケドニアがあるのに、南マケドニアと言う国はないという不思議。 歴史をひもとくと、ここにオスマントルコ帝国、オーストリアハンガリー帝国の支配だけではなく、アドリア海沿いにはヴェネツィア共和国の支配も絡み、かなり複雑。 日本の世界史の教科書では、このところを深く説明していないが、海外の観光ガイドを読むと、通常、その国の歴史にそれなりのページを割いているので、こういうのは、実際に足を運んで学ぶことなのかもしれない。 この点、日本の観光ガイドは、写真でページを埋めているので、内容が浅いものが多い。 昔、海外旅行をするときには、ハーバード大学の書籍部だか何だから発売しているLet's Go シリーズを持ち歩いたものだが、今思うと、あれで、英語を斜め読みするのが鍛えられた。 ビジネス表現に慣れるための勉強をするまでには、到らなかったが。
現在のボスニア国内でセルビア人が多く住んでいる地域は北部と南東部。上の地図では現在のボスニア北部と南部がクロアチア自治州に編入されているので、セルビア系の反発が大きかったと思う。 マケドニアはブルガリアから逃れたい一心でセルブ=クロアート=スローヴェン王国に参加し、モンテネグロは恐らく当時民族意識が希薄でセルビアに従属状態だったのだろう。現在のコソボがモンテネグロに属しているのは興味深い、
Wikipediaで調べたら、第二次世界大戦中にナチスドイツと組んで、クロアチア自治州なるものを作ったらしい。 その時の国境線がほぼ、現在のクロアチアの版図と重なる。
<以下、wikipediaより> https://ja.wikipedia.org/wiki/クロアチア
1918年に第一次世界大戦の敗北からオーストリア・ハンガリーが崩壊。オーストリア・ハンガリーから離脱したスロベニア人・クロアチア人・セルビア人国は、南スラブ民族による連邦国家の構成と言うセルビア王国の提案を受けて、セルブ=クロアート=スロヴェーン(セルビア・クロアチア・スロヴェニア)王国の成立に参加。1929年は国名をユーゴスラビア王国に改名した。しかしこの連邦国家にはクロアチア人側から、セルビア人に対して政府をコントロールしているのはセルビア人であるとする反発が大きく1939年にはこの不満を解消する目的で、広大なクロアチア自治州(セルビア・クロアチア語版、英語版)を設定したが、批判も多かった。
Wikipediaを読んでの想像だが、確かにかつてのベネチア共和国の海岸線の領土は、クロアチアに引き継がれている。 そして、クロアチア人はベネチア共和国の傭兵でもあったことから、ベネチアのアドリア海沿いの領土をオーストラリア・ハンガリー帝国に割譲した後、クロアチアに渡ったようである。
恐らくクロアチア人が中心になり、アドリア海沿岸のかつてのベネチア共和国領の大半を解放したとかで、その国境がハプスブルグ帝国に引き継がれた。スロベニアは人口比もあり、イストリア半島北部程度しか貢献できなかった。ボスニア・ヘルツェコビナのアドリア海側に住んでいるのはクロアチア系が多いが、オーストリア・ハンガリー帝国に属していたクロアチア領と異なりオスマン帝国の支配地域だったという歴史的経緯からボスニアに組み込まれてしまった、というところか。
地図を見ると、なんでクロアチアは、風光明媚であろうアドリア海の海岸線を寡占しているのか? スロベニアもボスニアも気の毒な気がする。
浜ちゃんのフォアボールにハラハラしながら観ているのもこれで、なくなるか。 ベイは投手が足りるのかな。各投手の球筋とか、伸びしろとか、見ていても良く分からないから、里崎チャンネルとかでの解説を待つとするか。
ヒマでヒマでマヒするくらいヒマなポランコはもう辛抱できなくなったか。
ポランコよ、⇧こういう風に言葉を文章にかけたりオチがあるのをダジャレと言う。 コンゴの伝染病の話題に『今後~』と書き込むのは単に同音異義語を書いただけで、ダジャレにすらなっていない。
文末語呂合わせをダジャレだと思い込むのも、恥ずかしいからいい加減やめなさい。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
禁断症状のホラ吹きザルが閑散とした東京に3連続投稿やな♪マンキー廃人大爆笑
>> 9064 英国は、原則、戦争に負けたことのない国(インドや香港からの撤兵等を除くと)。外圧や占領で国の形態が大きく変わり、辛酸を舐めながらも改革を強いられた経験がないことが大きな影響を与えているのではないか。 スペインが驚きなのは、最初の高速鉄道が1990年代に入ってからと日本の新幹線に遅れること30年近い。長年のフランコ独裁政権が終わり、バルセロナでオリンピックを開き、大きく変わっていった側面の一つだと思う。 日の沈まぬ国だったのが、欧州の最貧国にまで落ちぶれてから再起を図っている。鉄道の軌道もまちまちだったのに、高速鉄道敷設を進める気概はたいしたものだと思う。新しいもの好きの本性が、フランコ政権終焉に伴い、出てきたのか。
確かにスペインが中国に肉薄しているのは以外だが、スペイン人は概して新し物好きだからこういうものの導入に抵抗がないのかも。イギリスがランクインしていないのはその逆パターン。ロンドンとバーミンガム間という近距離への導入予定以外の計画がないらしい。電車好きに見えるドイツが積極的でないのはよくわからない。今後距離が伸びそうなのは長距離路線区間の多いトルコだろう。
中国の方が高速鉄道の距離が長いのは、国土の広さを考えると納得だが、スペインが2位なのは予想外だった。 発着の中心であるマドリッドは、国土のほぼ中心部にあり、日本のように細長くなく、まとまった国土なので、そんなに長い線路はないと思っていた。ちなみに、日本の約1.3倍の国土に日本の人口の約3分の1が住んでいる。 スペインの高速鉄道の大きな利点は、フリーゲージ列車を成功させたので、一部、従来の在来線の線路の上を高速鉄道が走れる事。日本でも山形新幹線の例があるが、スペインでは、日本のような狭軌がないので、標準軌のときのスピードを多少犠牲にすれば済んだのだが、日本では、狭軌でスペインのフリーゲージの技術導入が難しく、また、標準軌区間の最高スピードの関係で導入に到っていないらしい。
それでもなぜか、日本の新幹線はスペインで有名らしく、お土産に日本の新幹線の模型のオモチャを持っていったら喜ばれた。 あと日本のもので有名なのは、畳だろう。アンダルシア地方では、ところどころに畳ショップがある。スペイン語では、複数系をi で終える傾向があるので、tatami と言えば、複数で、1枚の畳は、tatamo と男性名詞で表現する。スペインの友人は、畳を1枚だけ買って、自分の寝床のベッドに使っていた。こういう使い方もあるんだと思った。
念の為、閉じ込めておいた。
>> 9060 これは失礼。こんな感じ?
ポランコはメタボが進みスーツはもう着れない。それでバカボンのパパみたいな恰好をして毎日だらだら過ごしているのだ。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
おやおや、色々教育的指導をしていたら、ポランコが出て来たぞ。
小人で検索して、もう一つ、故事を見つけてみた。
「小人の過つや必ず文る」***「論語」子張から
品性の卑しい人は過失を犯しても改めようとせず、言い訳をしてごまかそうとするという意味の慣用句 との説明をコピペ。 旅行の写真をアップしないのがこれを証明している。行っていないのなら行っていないと謝るのが通常の人間の対応。
読んでない、読んでない。(笑)
昔、大学の図書館やスポーツクラブにおいてあった時には、ただだから読んでいたが、自宅で取るには高過ぎる。
以前は、ヘラルドトリビューンが月5000円くらいだった気がするが、それがこれまでの最高値購読料かな。
フェイスブックの投稿からコピペしただけ。
FT読んでるの。すごいな~ 飛行機に乗る時他に選択肢がないと手にする事もあるが、大抵一面をチラ見して終わり。
4週間100円でその後9千円/月というのにややびびった。
笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
ホントだ、黒海ヨーグルトと言うべきだ。
ジョージアと言うのは、いまいちマイナーな地名なので、カスピ海を使ったのかもしれないと思った。
地球温暖化が進めば、この地域のヨーグルトもすぐに腐るようにならないか心配。
下のサイトを見ると、南欧では段々とワインの原料の栽培が出来なくなり、デンマークやロシアで栽培可能となるらしい。
https://www.ft.com/content/1c94c23a-90f1-465f-99c0-0c83f9b20b49?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1NhJLVjNpr2q9-DX4CLk9JcpeNZykAMo5-2zNYimwamY0Ul5XGihEjsmU_aem_pX37PxyImO-wEU_vcUgC9A
カスピ海ヨーグルトの起源はジョージア
https://www.caspia.jp/cywhat/roots/
ジョージアはカスピ海ではなく黒海に面しているので、黒海ヨーグルトと呼ぶのが正しい。黒はヨーグルトのイメージに合わず、地中海は遠すぎるのでカスピ海としたのか。グルジアヨーグルトでもよかったのだろうが、ブルガリアと被るので止めたのだろう。
コーカサスヨーグルトがそのまんまで分かり易いと思うのだが、ケフィア(=ヨーグルトきのこ)との混同を避けたか。
Tanti auguri di buon Anno!
そう言えば、カスピ海ヨーグルトの宣伝にコーカサス地方原産との説明があった気がする。
昔、バリ島で日本人の旅行者だけが良く腹をくだすと言われていたが、私は何度言っても大丈夫だった。
歯を磨くときにミネラルウォーターを使わなかったが、水道水はとても飲める代物ではなかった。シャワーの水も、海水を薄めたものを浴びているようだったし。
!Feliz Año Nuevo!
ジョージアのバツーミのビーチでは海水を飲まないよう気を付けよう。
カスピ海ヨーグルトの菌はカスピ海の水で培養されている訳でもなく、コーカサス地方原産という意味だから問題ないと思うけど。コーカサスや中央アジアでも基本気にせず飲み食いする予定。
ところで中央アジアに行くとたいていの日本人はお腹をやられ、理由は水ではないかとされている。歯を磨くの迄ミネラルウォーターを使ったのにやられたという話もある。恐らく料理に大量に使われる綿花油の消化酵素が少ないせいだと思う。
ジミー・カーター大統領は共和党の人間からも、その人間性は高く評価され the Great Manと言われているようである。
ロシアや中国に接する内海は何が流れ込んでいるか、全く信用ならない。放射能など垂れ流しの可能性もある。
以前、原子力に詳しい教授から聞いたのだが、福島から海に流れる放射能など、太平洋で拡散されて無視されるレベルだが、中国や北朝鮮の核実験で出る放射能は陸続きなので、韓国や香港の水でさえ放射能が混入しているはずだとのこと。
カスピ海ヨーグルトなどと宣伝している商品もあるが、とても買うつもりにならない。
EuropeのビーチリゾートへはLCCやチャーター便が頻繁に飛んでいるので、陸路の接続はそれ程問題にならない。黒海沿岸のリゾートがぱっとしない理由は、昔から安かろう。。。のイメージがあるのと、黒海の水質が地中海程綺麗ではない事。後者については断定はできないが、ウクライナ、ロシアから流れ込む河川の汚染に起因しているように思う。
>> 9086
そう言えば、カーター大統領は、退任後、選挙監視団を途上国に送る等のボランティア活動をしていたが、ブッシュとゴアの大統領選挙がもめたときに、自分の国の選挙に嫌気がさすとともに、恥の意識が芽生え、もう選挙監視ボランティアをしたくないと言ったのを覚えている。
最近でも米国は似たようなことがあったから、晩年、カーター大統領はどんな思いでいらしたであろうかと思ってしまう。
>> 9084
やはり、欧米から高速鉄道や高速道路でのアクセスが良くないと、リゾート地も垢抜けないのかもしれないのかな。
ちょうどさっきまでテレビで、日本の職人が、ギリシア、ルーマニア、ブルガリアの田舎町に行き、建物等の修繕をするという番組をやっていた。日本と違い、湿気が少ないからであろう、粗末な造りの家が多い印象だった。
カーター大統領は、在職中よりも元大統領としての功績が大きいことで有名。その功績でノーベル平和賞も受賞している。
英国はどうだか知らんが、米国大統領は、大統領を辞めた後、その立場を活かし、様々な活動に勤しむのが普通。オバマみたいに院政を敷して現職に影響を及ぼそうなんて、日本の元首相がやるようなセコイことをするのは例外の部類に入る。トランプ次期大統領もこの4年間、そのけがあったが、再選を目指していたということで別枠。
日本では、明治時代にグラント元大統領が来日したが、これも元大統領として清国と日本の仲介をしたり、明治天皇に様々な御進講をして、感謝されている。
ケネディ大統領は、若くして大統領になったので、大統領在任中のインタビューにて大統領退任後は、上院議員になって国に奉仕したいと答えている。
話をカーター大統領に戻すと、元大統領として、「キャンプ・デービッド合意」の仲介、金日成主席と会談し「米朝枠組み合意」の足掛かりを築いたり、カーターセンターを通じた様々な人権活動をするなど、元大統領としての活動は、傑出している。
He should have become ex-President without becoming President. と言われたくらいだ。
旅行がファーストクラスと五つ星ホテルの利用であることは疑いないが、それ以上に家族を含めた終身のシークレットサービスと年金にお金がかかる。これも最近、改正されて縮小されたか、される予定らしい。
なお、カーター大統領は、在職中に歳費をもらっていたが、ケネディ大統領とトランプ大統領は、在職中に歳費すらもらっていないらしい。(正確には、年収1ドルとかにしている。)
ジミー・カーターって印象が薄いと思ったら大統領の任期が77-81年とは、びっくり。トニーブレアとかもそうだけど若くして首相や大統領になった人は辞めた後何をしているのかが気になる。文化活動という名目でファーストクラスの世界旅行、高級ホテル滞在、グルメ三昧か。
笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
クロアチアの地中海沿岸はawesomeだね。しかし内陸に車で5キロも入るとgenuineになってくる。昨今モンテネグロはもちろんアルバニアのビーチも随分と垢ぬけてきたらしい。山道なのにガードレールがなくて見た目おっかないのは直ったかな?
ルーマニアやブルガリアのビーチにはもう長い間行ってないが、庶民的な雰囲気は余り変わっていない気がする。
来年夏のシルクロート旅行でトルコからジョージアへ黒海に沿って移動する予定なので、状況報告ができると思う。
バルカン諸国とバルカン半島の国とは違うのか。
Wikipediaをみたら、次のような記述があった。
『1991年6月から始まったユーゴスラヴィア崩壊の後、「バルカン」という用語は(特にクロアチアとスロヴェニアにおいて)ネガティブな政治的意味合いを持つようになり、世界的にも武力衝突と領土の断片化を指して自然に使用されるようになった(バルカニゼーションを参照)』
クロアチアは、旅行した人が綺麗な街だと言っていたので、awesomeなんだろう。
前述の地図には黒海沿岸がawesome areaに含まれていないなあ。世俗的には、まずエーゲ海を見てからにしろ、ということか。ナポリやソレントで地中海を眺めた時、一日中、ホテルの部屋から海を眺めていてもいいと思ったが、エーゲ海や黒海は、さらに異なる趣きが楽しめるのだと思っている。
所謂『バルカン』地域ね。バルカン半島にはギリシャやトルコのヨーロッパ側も含まれるが、『バルカン』地域には含まれない点に注意。スロベニア人やクロアチア人もこぞって自国は『バルカンに含まれない』と主張するだろう。そうなるとボスニア・ヘルツェコビナ、セルビア、モンテネグロ、コソボ、アルバニア、ブルガリアか。"awesome"は褒めすぎで、よく言って"genuine"くらいだと思う。
個人的にはルーマニア、ブルガリアの黒海沿岸が気に入っている。昭和の海水浴場を想い出させるという点で。ビーチリゾートならバルカンではないが、トルコのアンタルヤかギリシャのロードス島がいい。
カーター大統領が亡くなった。米国では、大統領経験者は大統領職を退いてからも、President 〇〇 と呼ぶことが多い。
アトランタにあるカーターセンターを訪れた時、立派な日本庭園があったのを覚えている。うちにも遊びに来たスペイン人がどういう経緯か、カーターセンターでスペインの料理をペラペラと紹介していたら、カーターセンターの料理を手伝うことになったということもあったっけ。
カーター大統領は、日本を訪れた初めての現職大統領で、昔、東海道線で東京からペリー来航の下田まで移動するので、線路沿いにものすごい数の警察官が配置されていたのを覚えている。
R.I.P.
>> 9078
アメリカ人の見ているヨーロッパは、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツくらいで
ヨーロッパ人の見るアメリカは、New Yorkとロサンゼルスだけだというジョークがあるが
グリーンガイドみたいなマーケット戦略に忠実であろう会社は、売れるところに絞っているのかもしれない。何しろ、ミシュラン発行なんだから。
東欧こそ、商業主義に毒されたツーリズム抜きに楽しめる真の旅行先との書き込みが、フェイスブックにあった。私も毒された一人ではあるが。
先日、紹介してくれた『異国の窓から』を先程、読み終わった。ドナウ川への憧憬とソ連時代の東欧のギスギスした雰囲気を上手く描写している紀行小説だ。
最後のローマのくだりは、自分が訪れた時を思い浮かべながら読めたが、東欧は未開拓なので、想像力を膨らませ堪能させていただきました。
失礼、正しくは、Roman Question でした。英語は、ラテン語からの訳語らしい。
日本訳のローマ問題に引かれて、間違えて記憶した。初めて読んだのは、グリーンガイドの英語版だったのだが。
ラテラノ条約によって解決したのは、ムッソリーニの偉業の一つ。
ムッソリーニは、ヴァチカンを認めるとか、マフィアの掃討とか、経済対策を含め、色々といいことをしたが、組んだ相手が悪かった。ヒトラーが見せたドイツ軍の一糸乱れぬ行進を見て、コレダ! と思ったらしい。
他方、フランコ将軍もヒトラーと一緒に戦うように延々と説得されたそうだが、ヒトラーを子ども扱いし、相手にしなかったとの記録が残っている。これを見ていた元ドイツ軍の関係者が言うには、役者が違うということだったらしい。
人間の器と言うのがリーダーの論評をするときなどに、よく言われるが、こういう時に露わになるのであろう。そして国全体の運命を決めてしまうのかもしれない。
フランコ将軍は、国民から選ばれておらず、ヒトラーとムッソリーニは、形式的には国民から選ばれているので、スペイン人は運が良く、ドイツ国民とイタリア国民は、自ら蒔いた種と言うことなのかもしれないが。
今は亡き書籍版のフライトプランナーや、LPを買いによく銀座の丸善迄行ったけど、Michelin Green Guideって手に取った事すらなかった。理由は旅行テリトリーだった東欧、旧ソ連やアラブ編が出版されていなかったから。
笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
Roman problem って何?
「I love Roma ❤」と書かれたTシャツを見て、びっくりする事ではないよね。
>> 9075
昔、書店で色々と見比べた時にLonely Planet も見たと思うが、確かMichelin Green Guideを買った。
日本で買ったか、アメリカで買ったかは覚えていない。
このグリーンガイドは、初めのぺ数ページが観光地の歴史を結構なボリュームで説明している。ローマの場合、Roman Problemのことも日本の教科書にはないのに、丁寧に説明されていて驚いた覚えがある。ちなみに先日、アメリカ人に聞いたら、アメリカの高校の教科書でもRoman Problemは出てこないだろうとのこと。ただ、大抵のインテリのアメリカ人は知っている。
最近は、欧州でも米国でも友人の家に泊まり歩き、無銭飲食を繰り返すのと、観光地に対する興味が薄れてきたので、ガイドブックを持ち歩かずに現地で適当に情報を集めたり、ネットで見て情報収集は終わりにする。そもそも、友人が案内してくれるし。
Let's goシリーズは読んでいたが、Lonely Planetの網羅性には敵わなかった。実際前者はパンデミックで廃刊に追い込まれたが後者は現存。ネットでかなりの情報を得られるようになった昨今、LPも営業的には苦戦はしていると思う。Iran, Turkey, Centra Asia編のLPをダウンロードして旅行の準備に読んでいるが、以前のように旅行に必須という感じではなくなった。
地球の歩き方中央アジア編の新刊が先月発売され早速ダウンロードしてみたが、ちらっと見て内容が薄いのを確認して以来開いていない。
笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
コソボと言うのは、「セルビア建国の地」と言われているが、住民の9割はアルバニア人。
セルビアとモンテネグロは、Wikipediaによると言語的、文化的には違いがないそうだが、コソボ紛争は、セルビア人とアルバニア人のゲリラとの戦いから始まったらしい?
それでもって、アルバニア人には、アルバニアと言う国が別に存在する。
そこに北マケドニアと言う国があるが、ブルガリア人は、マケドニアはブルガリアの一部だと思っているらしいし、第一、来たマケドニアがあるのに、南マケドニアと言う国はないという不思議。
歴史をひもとくと、ここにオスマントルコ帝国、オーストリアハンガリー帝国の支配だけではなく、アドリア海沿いにはヴェネツィア共和国の支配も絡み、かなり複雑。
日本の世界史の教科書では、このところを深く説明していないが、海外の観光ガイドを読むと、通常、その国の歴史にそれなりのページを割いているので、こういうのは、実際に足を運んで学ぶことなのかもしれない。
この点、日本の観光ガイドは、写真でページを埋めているので、内容が浅いものが多い。
昔、海外旅行をするときには、ハーバード大学の書籍部だか何だから発売しているLet's Go シリーズを持ち歩いたものだが、今思うと、あれで、英語を斜め読みするのが鍛えられた。
ビジネス表現に慣れるための勉強をするまでには、到らなかったが。
現在のボスニア国内でセルビア人が多く住んでいる地域は北部と南東部。上の地図では現在のボスニア北部と南部がクロアチア自治州に編入されているので、セルビア系の反発が大きかったと思う。
マケドニアはブルガリアから逃れたい一心でセルブ=クロアート=スローヴェン王国に参加し、モンテネグロは恐らく当時民族意識が希薄でセルビアに従属状態だったのだろう。現在のコソボがモンテネグロに属しているのは興味深い、
Wikipediaで調べたら、第二次世界大戦中にナチスドイツと組んで、クロアチア自治州なるものを作ったらしい。
その時の国境線がほぼ、現在のクロアチアの版図と重なる。
<以下、wikipediaより>
https://ja.wikipedia.org/wiki/クロアチア
1918年に第一次世界大戦の敗北からオーストリア・ハンガリーが崩壊。オーストリア・ハンガリーから離脱したスロベニア人・クロアチア人・セルビア人国は、南スラブ民族による連邦国家の構成と言うセルビア王国の提案を受けて、セルブ=クロアート=スロヴェーン(セルビア・クロアチア・スロヴェニア)王国の成立に参加。1929年は国名をユーゴスラビア王国に改名した。しかしこの連邦国家にはクロアチア人側から、セルビア人に対して政府をコントロールしているのはセルビア人であるとする反発が大きく1939年にはこの不満を解消する目的で、広大なクロアチア自治州(セルビア・クロアチア語版、英語版)を設定したが、批判も多かった。
Wikipediaを読んでの想像だが、確かにかつてのベネチア共和国の海岸線の領土は、クロアチアに引き継がれている。

そして、クロアチア人はベネチア共和国の傭兵でもあったことから、ベネチアのアドリア海沿いの領土をオーストラリア・ハンガリー帝国に割譲した後、クロアチアに渡ったようである。
恐らくクロアチア人が中心になり、アドリア海沿岸のかつてのベネチア共和国領の大半を解放したとかで、その国境がハプスブルグ帝国に引き継がれた。スロベニアは人口比もあり、イストリア半島北部程度しか貢献できなかった。ボスニア・ヘルツェコビナのアドリア海側に住んでいるのはクロアチア系が多いが、オーストリア・ハンガリー帝国に属していたクロアチア領と異なりオスマン帝国の支配地域だったという歴史的経緯からボスニアに組み込まれてしまった、というところか。
地図を見ると、なんでクロアチアは、風光明媚であろうアドリア海の海岸線を寡占しているのか?
スロベニアもボスニアも気の毒な気がする。
浜ちゃんのフォアボールにハラハラしながら観ているのもこれで、なくなるか。
ベイは投手が足りるのかな。各投手の球筋とか、伸びしろとか、見ていても良く分からないから、里崎チャンネルとかでの解説を待つとするか。
ヒマでヒマでマヒするくらいヒマなポランコはもう辛抱できなくなったか。
ポランコよ、⇧こういう風に言葉を文章にかけたりオチがあるのをダジャレと言う。
コンゴの伝染病の話題に『今後~』と書き込むのは単に同音異義語を書いただけで、ダジャレにすらなっていない。
文末語呂合わせをダジャレだと思い込むのも、恥ずかしいからいい加減やめなさい。
笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
禁断症状のホラ吹きザルが閑散とした東京に3連続投稿やな♪マンキー廃人大爆笑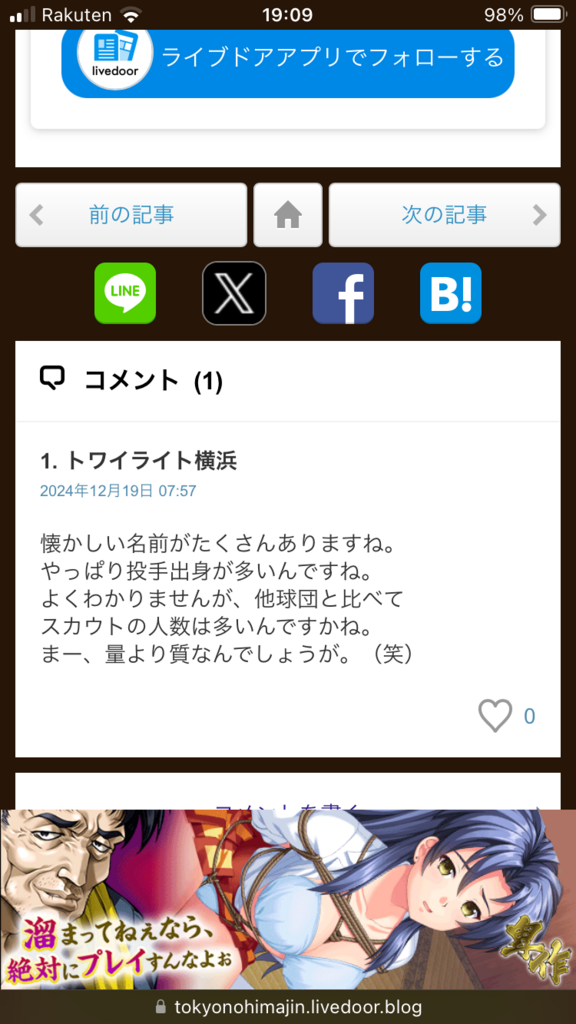
>> 9064
英国は、原則、戦争に負けたことのない国(インドや香港からの撤兵等を除くと)。外圧や占領で国の形態が大きく変わり、辛酸を舐めながらも改革を強いられた経験がないことが大きな影響を与えているのではないか。
スペインが驚きなのは、最初の高速鉄道が1990年代に入ってからと日本の新幹線に遅れること30年近い。長年のフランコ独裁政権が終わり、バルセロナでオリンピックを開き、大きく変わっていった側面の一つだと思う。
日の沈まぬ国だったのが、欧州の最貧国にまで落ちぶれてから再起を図っている。鉄道の軌道もまちまちだったのに、高速鉄道敷設を進める気概はたいしたものだと思う。新しいもの好きの本性が、フランコ政権終焉に伴い、出てきたのか。
確かにスペインが中国に肉薄しているのは以外だが、スペイン人は概して新し物好きだからこういうものの導入に抵抗がないのかも。イギリスがランクインしていないのはその逆パターン。ロンドンとバーミンガム間という近距離への導入予定以外の計画がないらしい。電車好きに見えるドイツが積極的でないのはよくわからない。今後距離が伸びそうなのは長距離路線区間の多いトルコだろう。
中国の方が高速鉄道の距離が長いのは、国土の広さを考えると納得だが、スペインが2位なのは予想外だった。
発着の中心であるマドリッドは、国土のほぼ中心部にあり、日本のように細長くなく、まとまった国土なので、そんなに長い線路はないと思っていた。ちなみに、日本の約1.3倍の国土に日本の人口の約3分の1が住んでいる。
スペインの高速鉄道の大きな利点は、フリーゲージ列車を成功させたので、一部、従来の在来線の線路の上を高速鉄道が走れる事。日本でも山形新幹線の例があるが、スペインでは、日本のような狭軌がないので、標準軌のときのスピードを多少犠牲にすれば済んだのだが、日本では、狭軌でスペインのフリーゲージの技術導入が難しく、また、標準軌区間の最高スピードの関係で導入に到っていないらしい。
それでもなぜか、日本の新幹線はスペインで有名らしく、お土産に日本の新幹線の模型のオモチャを持っていったら喜ばれた。
あと日本のもので有名なのは、畳だろう。アンダルシア地方では、ところどころに畳ショップがある。スペイン語では、複数系をi で終える傾向があるので、tatami と言えば、複数で、1枚の畳は、tatamo と男性名詞で表現する。スペインの友人は、畳を1枚だけ買って、自分の寝床のベッドに使っていた。こういう使い方もあるんだと思った。
念の為、閉じ込めておいた。
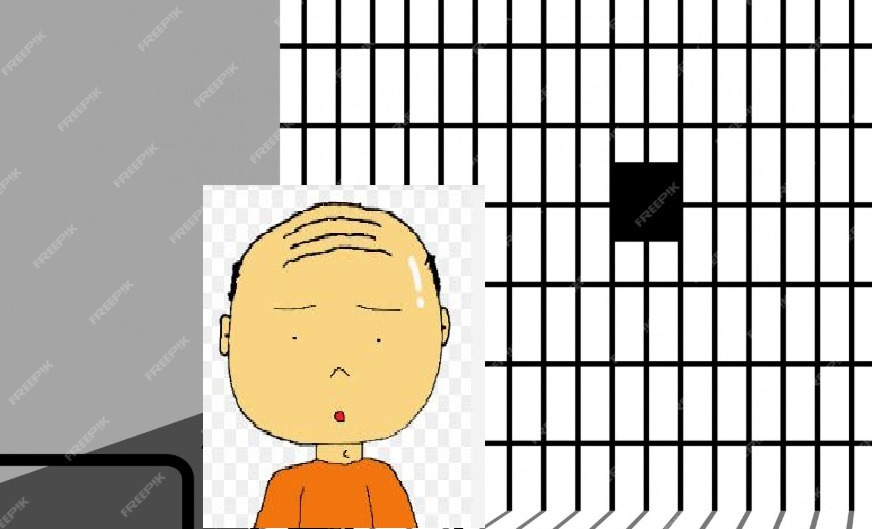
>> 9060

これは失礼。こんな感じ?
ポランコはメタボが進みスーツはもう着れない。それでバカボンのパパみたいな恰好をして毎日だらだら過ごしているのだ。
笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
おやおや、色々教育的指導をしていたら、ポランコが出て来たぞ。
小人で検索して、もう一つ、故事を見つけてみた。
「小人の過つや必ず文る」***「論語」子張から
品性の卑しい人は過失を犯しても改めようとせず、言い訳をしてごまかそうとするという意味の慣用句 との説明をコピペ。
旅行の写真をアップしないのがこれを証明している。行っていないのなら行っていないと謝るのが通常の人間の対応。