>> 9377 海鮮料理と言うのは、日本でも主に外食が中心だから、家庭料理とは別物なのかもしれない。 ドナウの水は、料理に使えるのであろうか。また、降雨量は、草木が育つのに十分であろうか。 ググってみたら、次のように出て来た。 『ハンガリーは農業大国として知られ、小麦やとうもろこし、ひまわり種、牛乳、豚肉などの生産が盛ん。また、フォワグラの生産でも世界的に有名です』
古代から肥沃な大地からできる様々な農作物で家庭料理が発達したのかな、とか考えました。
調べてみたが予想通り、2024年の日本のデジタル赤字は、6兆6,507億円で、インバウンドによる旅行収支の黒字額を吹っ飛ばす金額で、これだけを見ると発展途上国型のサービス収支と言える。 一方、対米貿易黒字額は、2024年で日本の対米貿易収支、前年比0.9%減の8兆6281億円の黒字。輸出額は過去最大の107兆879億円を記録。 貿易収支は主に、農産物と製造業、サービス収支はハイテク産業だろうから、産業構造は勿論、選挙民の層も地域も異なるだろう。 トランプ大統領の方針は、クリントン政権のときから始めた製造業よりもIT産業を優先し、国の経済を反映させると言う方針の大転換である。IT産業でアメリカ経済は、繁栄を謳歌し続けているが、その一方で、格差は拡大し、製造業を支えるプアーホワイトと言われる人たちの不満を吸い上げると言う点で、民意に沿っていると言える。 もっとも、格差の拡大を関税政策で対処すると言うのは、IT産業がここまで国の経済の大部分を占めている現在、無理ゲーだと言うのが多くの専門家の指摘するところ。また、IT産業への構造転換が遅れた日本にとっては、実はあまり影響がないのではないかと言う指摘もあるがどうなんだろう。 ここからは、私の考えだが、格差の拡大を関税政策による製造業復活と言うのは、国際的なサプライチェーンが複雑に絡み合う現在では、一朝一夕にできるものではない。アメリカの次の中間選挙どころか、任期中にも無理であろう。 宗教的な信仰から来る自己責任論から強い反発があるであろうが、社会福祉等を充実させる方向に持って行くのが解決策の一つだとは思う。その為には、福祉にただ乗りしようとする不法移民の対処も問題になるであろうが。
ハンガリー料理について率直な感想を述べると、レストランで食べるハンガリー料理はおいしくないが家庭料理はびっくりする程おいしい。 例えば前菜は鶏ガラで作った肉スープ、メインは Pörkölt というパプリカで牛肉もしくは豚肉を煮込んだシチューに手づくりのニョッキを付け合わせる。これと薄い輪切りにして甘酢にさらしキュウリサラダが抜群の相性。ちなみ周辺国でメインで食されるグーラッシュは Pörkölt のバリエーションで、ハンガリーの Gulyas はスープ扱い。
トランプが日本に24%の関税を掛けると言っているのは、日本がアメリカに対し46%の関税を掛けているという理由らしい。そんな事実はない訳だが、この46%という数字は日本の貿易黒字額を日本からアメリカへの輸出額で割ったレートとの事。つまり貿易黒字を減らせばトランプ関税も下がるという図式。
GAFA企業が日本で法人税を払わずに挙げている利益を貿易黒字額から引いてもらえないものだろうか。
東欧の本を読んでから、やたらとバルカン半島付近の情報が目につくようになったためか、テレビ番組にも気が付いた。 途中から見たが、ハンガリーが独立を勝ち取った後、その喜びを様々な建築の装飾で表現したこととか、街の美しさとかを取り上げていた。 そう言えば、大阪万博でもハンガリー料理が初日は人気が一番だとかリポートしたテレビ番組があった。 海のない国に、そんなに美味しい料理があるものなのかと思うのは偏見であろうか。
この番組について事前に知人から知らされていたが、時間を間違えて大河を見てしまった。以前はこのような時にアジア系違〇サイトで動画を見つける事ができたが、そういうのは一掃されてしまった模様。予告編と5分間のダイジェスト版のようなドローン映像だけ見れた。
赤沢大臣が交渉するらしいが、日本の取る関税交渉は、
1)個別にアメリカと交渉し、他の国々に抜け駆けと言われようが、さっさと妥協点を決めてしまうやりかたであろうか。アメリカは、ガキ大将的なところがあり、各国と個別に交渉するのを好む。特に、この傾向は、ディールを好むトランプ政権では顕著だ。 アメリカ政府が、日本と初めに交渉すると発表したのは、こうした日本政府の足元を見透かしているからであろう。
2)ガキ大将と対峙するのに一番効果的なのは、多国間交渉にアメリカを巻き込むことだ。ガキ大将のワガママが多数決の論理で抑制できるからである。これが嫌だから、トランプ政権はTPPから離脱した。 多国間交渉を行う為には、他の国々と共同歩調をとり、事前に十分示し合わせなければならない。また、日本は、EU、英国と対等な話し合いができるとは思えないし、上手く利用されてしまう恐れがあるので、これも国益に沿った交渉ができるかは未知数だ。
3)もう一つの方法は、アメリカに代わる貿易相手を探すこと。中国のことが石破政権の念頭にはあると思うが、これも一筋縄ではいかないだろう。一度、中国みたいな国に依存してしまうと、弱みを握られたような状態になり、散々利用されても抜けられなくなる恐れがある。 一方で、長い歴史と地理的状況を考えると、中国と言うのは適度な距離感を持って付き合って損のない国である。ロシアやアメリカよりも、数百年単位で考えれば、信頼できる国とも言えなくはない。
と言うことで、1)の方法で、大臣は、少しいじめられて、半べそかきながら交渉を終え、石破総理がドンマイと慰めると言うふうになるのではないか。 もしも、この過程で希望を持つとしたら、外圧を利用して、日本の農政改革が始まることくらいであろう。
さっきハンガリーの世界遺産を紹介した番組を見ていたが、1867年の独立までは、オスマントルコ帝国に続きオーストリアに支配されていたので、独立時の喜びは大きく、その象徴となる国会議事堂を立派に建造したので、現在は世界遺産になっているとかいう説明だった。考えて見ると、日本は異民族の侵入や支配が殆どなかったが、それでも、白村江の戦いで敗れてから100年以上、そして、弘安の役の後の50年くらいは防人や元寇防塁等、それなりに国防意識が高かった時期がある。 1867年にようやく独立し、それから100年も経たないうちにソ連による抑圧の期間があり、さらに現在でも不法移民の流入に目を光らせる必要がある国では、国境警備や国防、そしてその為の外交に対する国民の意識は異なるんだろうと思う。 それにしては、日本はノンビリしているが、ウクライナみたいにならないか、さすがに心配になってきた。
ポランコは暇に任せて青の掲示板への復帰を目論んでいる。 たけちゃんマンとかにまた気持ちの悪い忖度をしてすり寄るのだろう。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
>> 9369 言われて青の掲示板を見てみたら、荒れていた。 本日は、ホラダンス氏の書き込みもあって、雨で中止か。 最近、ホラダンス氏は、朝、チョコっとゴミ出しの後に書き込んでいるようだ。控えめにしたのが、ベイスターズが落ち込まない理由かもしれない。
勝負は下駄を履く迄わからないというのは将に今日の試合。
青の掲示版は大荒れの模様だが、7回92球零点のケイを8回から替えたのは、ケイ自身に何か原因があったと思いたい。開幕前のオープン戦や2軍戦に一時期投げない期間があったのがその根拠。そうではなく、単に石田裕太郎に回跨ぎを再度試させたいという理由なら、オープン戦気分でペナントレースを戦うなと言われてしまう。
梶原があのセンタ~ライナ~を取っていればというのはたらればか。とりあえず連敗は4で止まった。
なるほど。納得。解説ありがとうございます。 明日からのヤクルト戦で、つばみは、どう振る舞うかな
>> 9366
その通り、ストーカーだな、ジャビットは^_^
ところでジャビットがつば九郎の真似とは?
クルリンパをやったとか。
ナオキの写真を見る限り、ディアナ?に対するストーカー行為かも。
なんだ、ポランコが昨日の試合前に投稿していたとは。どうりで勝ち試合のいい流れが断ち切られた訳だ。
引き分けになった理由は山本と甲斐の勝負所のリードの差もあった。8回の表に山本は追い込んだカウントから外角一辺倒のリードとなり、甲斐に同点打を狙い打たれた。甲斐は9回の裏ピンチの場面、高梨に内角をつかせて筒香を打ち取った。
しかしオ~スティンが抜けた途端にピストル打線もいいところ。去年のあの左の外人と契約延長しなかったなら、代わりを取らないと駄目だろう。
昨日は勝ちゲームを落としてしまった気がしてならない。 久しぶりに青の掲示板を見たら、案の定😩 誰も『いいね』をクリックしていないところから見ると、ミソッカスなのか
昨晩は、久しぶりに勝ちゲームを見られなかったのでは。 ところでジャビットがつば九郎の真似とは? スタジアムに行かないと分からないのかもしれず、すみません。
ジャビット、つば九郎の真似
もしハンガリーで何かを思い出すとしたら、世界史で習ったオーストリアハンガリー帝国だろう。東ローマ帝国が滅びてから色々な帝国がエウロパには出現したが、18世紀には共和制の国家、アメリカが出現し、1867年に出来たオーストリアハンガリー帝国は、最後の方の帝国の出現だろう。1867年と言えば、江戸時代の最終章。日本は海に囲まれているから、エウロパとは異なるが、この時に、蝦夷地を統合し大日本帝国としたのと、マジャール人の地域を併合してオーストリアハンガリー帝国としたのは、同じうよなものなのかどうか。大きく異なるのは、日本は万世一系の天皇家が2千年以上も続いているのに対し、エウロパの君主は、日本で言えば武家将軍に過ぎず、征夷大将軍にはなっていない。
最終回、牧、佐野、筒香で三凡とは寂しい。筒香の打撃が一向にあがってこない。昨年、日本シリーズできっかけを掴んだとか言っていたのは何だったのだろうか。捕手が甲斐なので、攻め方も分かっていると思うのだが。
ルーマニアはコマネチ、ブルガリアはヨーグルトが日本人にとってピンと来るところだろう。一方、ハンガリーにはこれと言ったものがない、というか知られていない。初めて行く前はそういうミステリアスなところに惹かれたのかもしれない。それで行ってみて現実を目の当たりにして、大きなショックを受けたのは今や昔。
あ、ホントだ、ハンガリーとブルガリアを間違えていた。失礼。 チェコスロバキアは、ヒトラーがミュンヘン会談で併合したからドイツに近いと分かるが ルーマニア、ハンガリー、ブルガリアはごちゃ混ぜになっていた。
日曜日に試合に負けると月曜日に試合がないので、負けた悔しさを火曜日まで引きづり嫌だと、南場オーナーが言っていたが、心情はいかに。
2番目のくだりは旧ユーゴをハンガリーと言っているようなので、
これは自分の勘違い。ソフィアに地下鉄が出来たのは割と最近で自分が行った頃はまだなかった。それでいつのまにかブルガリアに地下鉄がない=旧ユーゴにはあるという論理になっていた。しかし旧ユーゴとアルバニアに地下鉄がないというのがこの話題の前提で、2番目の文章のハンガリーもブルガリアを指している。
ちなみにハンガリー、ブダペストの地下鉄の歴史は古く、空港方面へ延びる2号線に旧ソ連製の車両がお色直しされて運用されている。
ん、ハンガリーとブルガリアをまた書き違えている。2番目のくだりは旧ユーゴをハンガリーと言っているようなので、国旗が似ているとかいう問題ではなさそう。あの辺の旧社会主義諸国はいっしょくたに思えてしまうのか。アメリカ第一主義の影響かもね。
去年よく見られた平凡なフライとかなんでもない送球をポロっと落とすのに始まり、デナのエラーはレベルの低いのが多かった。今年はそれに拍車がかかって相手が爆笑もしくは大よろこびしそうな内容になっている。例えば中日戦で筒香がバックホーム送球する代わりにグラブでボールを上に放り上げたり、阪神戦で牧がぼてぼての当たりをとりそこねた挙句すねでボールを蹴ったり。観ていないがこの広島戦でも守乱に陥ったようで、そんな内容のオンパレードでは。
バルカン半島にハンガリーが含まれているか、良く分からなかったのだが、調べたら入っている。 以前も書いたように、地下鉄は、戦時のシェルターの役割を果たすので、バルカン半島でハンガリー以外の国になかったのは意外だった。ウクライナでも、時々、地下鉄の駅に非難する人達の映像が出てくる。
ところで、DeNAも日ハムも守備を強化したと言った割には、失策が多い。野球は、まずは守備から。そして、相手のミスにつけ込むことができるチームが強い。この後、どうなっていくのか、注意深く見守りたい。 ところで、株価が急落しているが、ホラ吹きホラダンス氏はどうしているのだろう。
これを見ると、バルカン半島には、地下鉄がないんだな
ブルガリアにはあるね。ソフィアのようにのんびり見える首都に地下鉄が開業している事自体驚きだが。
首都以外に地下鉄のある国に絞れば、イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、ギリシャ、ポルトガルくらい。調べてみたらスイスの首都ベルン及びチューリッヒに地下鉄はなく、ローザンヌにあるとの事。
ベイスターズも日ハムも負けたので、エウロパの地下鉄の話でも投稿しよう これを見ると、バルカン半島には、地下鉄がないんだな
あの場面、VTRを見てアレっと思ったのは同感。 ネットで記事を調べてみたら、一応,捕手も抗議したようだが、その間にテレビでは、VTRが流れていたのだろう。 ヤスアキは、復活したのか、どうなのか、良く分からない。 いつものように打たれれば、以前からダメだったと後追いの記事が出るであろうし、好調が続けば、その逆であろう。 こういう時には、江川卓氏のポジショントークではない解説等を聞いてみたい。
https://www.ronspo.com/articles/2025/2025040402/
不可解判定?いや“誤審”です…阪神の藤川監督が球審に確認するもファウル判定の1球に泣いて引き分けを挟み3連敗…OBからは「リクエストの適用範囲を拡大すべきでは?」の声も 2025.04.04 07:43 阪神が3日、京セラドーム大阪での横浜DeNA戦に2-5で敗れ引き分けを挟んで3連敗を喫した。焦点となったのは9回一死一塁からハビー・ゲラ(29)が佐野恵太(30)に2-2から投じた1球。明らかに空振りを奪ったが、ファウルの不可解判定を下されて三振が一転、四球となり、直後に勝ち越し点を奪われた。同点で迎えた9回にはクローザー投入のセオリーを無視した藤川球児監督(44)の采配も含めて、物議を醸す虎ファンにとって後味の悪い敗戦となった。
ファウルチップの有無やハーフスイングはリクエストの適用外
不可解判定?いや明らかな誤審だ。 8回に佐藤の起死回生の2号2ランで2-2の同点に追いついた阪神は9回のマウンドにゲラを送り込んだ。一死から宮崎にレフト前ヒットを許して佐野を迎えた。カウント2-2から、ゲラが投じた9球目、外角低めのボールゾーンに落ちるスプリットに佐野のバットは空を切った。だが、今季初スタメンに抜擢された栄枝のミットからボールがこぼれてしまった。ゲラも栄枝も三振だと確信していたが、真鍋球審はファウルの判定を下して、佐野が打席へ戻ったのだ。 栄枝がボールがバットに触れていないことを訴え、藤川監督も静かにベンチから出て、真鍋球審に確認作業を行った。真鍋球審は3人の塁審を集めて協議したが、ファウルチップかどうかは一番近くにいる球審の判断が優先される。しかも、真鍋球審が責任審判。判定が覆ることはなかった。中継局では、繰り返しスロー映像が流れたが、佐野のバットは、まったくボールに触っていなかった。不可解判定どころか誤審である。 だが、リクエストの適用範囲にストライク、ボールの判定やハーフスイング、及びファウルかどうかの判定は含まれていない。メジャーのチャレンジに倣って導入された制度だけに、メジャー同様にそこは適用外の部分。藤川監督もビデオ検証を求めることはできなかった。 だが、この1球が命運を分けた。佐野に11球粘られた末に四球を与え、続く山本に前進守備を敷いていた近本の頭上を抜く、2点タイムリー三塁打を浴びた。さらに1軍に昇格したばかりの伊藤将にスイッチしたが、森の浅いセンターフライでタッチアップを許して3点差。9回も反撃できず引き分けを挟んで3連敗となった。 スポーツ各紙の報道によると藤川監督は、「空振りだと思うんですけどね。すごく大事な1球でしたね」と、この判定に疑問を投げかけたという。 公認野球規則では、抗議は認められていないため、あくまでも確認作業になるが、藤川監督が、執拗に審判に食い下がらなかったのは、ゲラがマウンドで長い時間放置されて調子を崩すことを懸念したのだという。 阪神OBである評論家の池田親興氏は、「映像を見る限り、空振りに見えますが、球審は、ファウルチップの音や目で確認したのではなく栄枝が捕球できなかったということでファウルと判断したのでしょう」とした上で、こう提言した。
「人間が判断することなのでミスがある。それを正す意味でメジャーでチャレンジ制度が始まり、日本も追随した。ただ日本はすべてそのままメジャーの真似をする必要はないと思う。試合の進行を遅らせることになるので、ストライク、ボールの判定は別にして、今日のようなファウルの有無は、リクエストの対象に加えていいのではないか。メジャーのマイナーではストライク、ボールにAI判定が導入され、メジャーでも今季のオープン戦では試験的に使われていた。AI判定に関してもメジャーの後追いをするのではなく日本が独自に先に採用を検討していいのでは?」 確かにリクエスト制度が導入されてもまだ残るグレーゾーンになんらかのメスを入れる必要がある。 ただ今回の不可解な判定に関しては、阪神は意見書をNPBに提出するなど、フロントが抗議行動を見せる必要があるだろう。そして“誤審騒動”に隠れたが、9回にゲラ投入という継投策にも疑問は残った。 セオリーでいえばホームゲームで同点の9回はクローザーを投入する。 岡田前監督は、調子と、相手チームの打線や相性などを見極めながら、岩崎とゲラのクローザーを使いわけていた。時には、岩崎-ゲラの順での起用もあった。だが、藤川監督は、開幕から岩崎をクローザーとして起用してきた。しかも、ゲラは連投で、昨日は、スピードは出ていたが、ストレートは高めに浮き、変化球が制御できず、4安打、3失点していた。セオリーであれば9回は岩崎だったはずだ。 9回はオースティン、宮崎と右打者が続く打順。前日の借りを返させて、いいイメージを取り返すためにゲラを起用したのかもしれないが、腑に落ちない継投策だった。 だが、池田氏は、「この継投策は間違ってはいない」と藤川采配を支持した。 「阪神がクローザーを誰にするかもまだ序盤で手探りだろう。延長を考え、ゲラのブルペンでの調子、打線の巡り、そして長いシーズンを考えて昨日の失敗を取り戻させておきたいなど、様々な理由から藤川監督が判断したんだと思う。ゲラを先に使ったことには、超一流のクローザーだった藤川監督だからこその采配理由があったように感じる。判定の問題もあって結果的に失敗したが、それをもってこの継投が間違いだったとは言えない。十分に考えられる継投策だった」 移動日なしで、今日4日からは東京ドームに乗り込んで昨年のリーグ覇者、巨人との3連戦。開幕2つ目のカードを負け越した藤川監督は、どうチームの舵を取るのだろうか。
今日の阪神戦で勝敗を分けたのは九回表打者佐野の2-2からのスィング。判定はファールチップだが、VTRで見る限りバットにあたっていない。しかし捕手がその投球を捕球できなかった。それで佐野は駄目元でバットに当たったとアピールしたらそれが通ってしまったという事ではないだろうか。そのシーンは画面に映っていなかった。もしそうだとしたら判定後の捕手のリアクションは余りにもあっさりとしていたが。。。 去年59試合投げて抑えもこなし自責点10だった阪神のゲラだが、今年は3試合で早くも自責点6。 ヤスアキは9回の裏150Kを連発していたが、直球の威力が復活したのかはたまたスピードガンのバグか
勝手な思い込みだが、巨人はそのうち、落ちてくるだろうが、阪神に勝っておきたい。 オースティンはジャクソンに、話しかけるであろうか。
昨日の巨人戦に先発した石川が勝ち投手になった。相手が手負いのヤクルトとは言え良く投げたと思う。大きなテークバックからの直球が上ずり気味になるのは相変わらずだったが、緩急が利いていた。 かつてイチローが同時期にメジャーで活躍した長谷川滋利について「小さなテークバックからピュッと球が出てくるので打ちにくい」と言っていたが、その逆バージョンか。
対策としては昨日の中日戦メヒア相手のような早打ちではなく、待球して四球絡みで自滅させたいところ。
新浦は巨人時代「ノミの心臓」と呼ばれていたそうで、投手コーチと捕手に加え長嶋と王を含む野手全員が間近に来ると却ってプレッシャーを掛けるという配慮もあったのでは。
**** 記事では確か王は来ても長嶋は来ないとあったと思うが、長嶋茂雄氏には、そう言う配慮があったのかもしれない。選手時代の王には、味方が大量リードしているのにも拘わらず、ちょっと打たれると委縮した新浦投手に対し、「スコアボードを見ろ」と言われたと言う逸話があるらしい。
オースティンの打席以外の挙動は、これまであまり見ていなかったので、これから注意してみようと思う。見逃すかもしれないので、新たな発見があったら教えてください。
バウアーとオースティンの場合は助人でネーティブ同士なので状況が異なる。オースティンは去年ジャクソンやケイがピンチに陥った時、日本人の輪が解けた後一言二言声掛けしていたように思う。ロペスに至ってはストライクが入らないエスコバ―をどやしつけていた。
巨人にいた新浦投手の連載に書かれていたが、昔、新浦投手がマウンドでピンチになり他の内野手が集まっても長嶋茂雄三塁手だけは来なかったらしい。それは別に新浦が嫌いなわけではなく、プレイに集中していたからだったと新浦は書いていた。オースティンの場合も同様な理由ということはあるであろうか。
チャット GPT に聞いてみたら 不仲ではないということになっていたが。
本日の試合4回の表ノーアウト満塁のピンチの場面。大原投手コーチが通訳と共にマウンドに駆け寄り、内野手全員がバウアーの廻りを囲む。オースティンはというと、最も遠目の位置にいて手持無沙汰ぽさを隠すかのように、マウンドの土を手でならしていた。人の輪が解ける時にバウアーへの声掛けもなし。やはり不仲説は本当なのか?
本日は、大リーグにNPB、選抜高校野球と盛りだくさんだ。 日本では野球は大学野球から始まっており、そして、昔は大学野球が一番の人気だった。 競技名を野球と名付けたのも東京大学野球部だし(正岡子規等、諸説あり)、天皇杯はいまだに六大学野球に授与される。 その次が高校野球で、阪神電気鉄道が甲子園を建造し、無料で高校野球大会のために誘致したのが成功し、現在でも使用料は無料らしい。 甲子園で優勝した時の盾と言うのは、優勝校が入り口に堂々と飾っていたりする。 高校野球の後にようやく戦後になって、六大学野球のスターだった長嶋茂雄氏の活躍等により人気が出来ていたのがNPBで、大リーグに興味を持ち始めたのは近年のことだ。 これらの順序は、現在では、逆になっているのかもしれない。
面白い順に言わせていただくと、高校野球とNPB、それからメジャーと大学野球だ。 メジャーは、内野の守備が堅固過ぎるためなのか、スモールベースボールが少ない。恐らく、作戦として考えると成功の確率が低くなるのではないか。必然的に、長打偏向となる。加えて、ピッチクロックは、見ていて気になって仕方がない。やめてほしい。試合時間短縮の為であれば、高校野球ほどでなくても、打席の交代時の時間を短縮する等、やることはあると思う。 かといってNPBは、少し遅いと思う。この前、ドジャースとカブスの試合を観ていたが、テレビコマーシャルの時間が攻守交替の時間にギリギリ入る感じだった。それだけ、メジャーの方が素早く交代するのであろう。 思うに、NPBでは、投手や打者が構えてから、プレートやバッターボックスを外すのを制限したらよいのではないか。 ところで、高校野球は非常に速いペースで試合が進むため、監督は素早い決断を迫られるそうである。
またまたアメリカネタ。 グリーンランドでは、こんな帽子があるとのmeme。
昔の選手は、大した給料はもらっていないと思う。この前、何かで聞いたが、堀内投手が現役時代、年収500万円くらいだったらしい。(最高のときで1800万円)これでは年金がないと厳しいだろう。特に当時は、所得税の最高税率は高かったし。 鈴木尚典コーチの年収をこの前見たが、選手時代の合計が18億円らしい。活躍に比して随分少ないと思うが、この頃に米田氏が活躍していれば、資産額も違っていたと思う。 それよりも実名でニュースになるのは、常連だったのか、何か特別なことがあったのか。そもそも認知症を疑う投稿もあるが、どうなんだろう。 最近は、甲子園に出場する名門校でも監督が学業や大学進学等にも気を配るようになってきた。岡田元阪神監督も、高校卒業後にすぐに育成契約を結びプロ入りする球児に対して警笛を鳴らしている。 高校卒業後、プロに入った米田氏がどうだったかは知らないが、スポーツ馬鹿だったとは思いたくない。
名球会・殿堂入りしている米田哲也が缶チューハイの万引きで逮捕とは。プロ野球機構に年金制度がないので、充分に貯蓄していない限り老後の生活は苦しいか。
前にも書いたが三浦の良さはベンチで泰然自若としているところ。それ以外の良さは特にないのかもしれない。でもどこか芯が通っていないとあのようには振舞えない。ベンチにどんと座って細かいところはコーチに委ね、選手の自主性を尊重する。フロントがいい選手を集めれはそれで結果は出るはずと思っているのだろう。
>> 9377
海鮮料理と言うのは、日本でも主に外食が中心だから、家庭料理とは別物なのかもしれない。
ドナウの水は、料理に使えるのであろうか。また、降雨量は、草木が育つのに十分であろうか。
ググってみたら、次のように出て来た。
『ハンガリーは農業大国として知られ、小麦やとうもろこし、ひまわり種、牛乳、豚肉などの生産が盛ん。また、フォワグラの生産でも世界的に有名です』
古代から肥沃な大地からできる様々な農作物で家庭料理が発達したのかな、とか考えました。
調べてみたが予想通り、2024年の日本のデジタル赤字は、6兆6,507億円で、インバウンドによる旅行収支の黒字額を吹っ飛ばす金額で、これだけを見ると発展途上国型のサービス収支と言える。
一方、対米貿易黒字額は、2024年で日本の対米貿易収支、前年比0.9%減の8兆6281億円の黒字。輸出額は過去最大の107兆879億円を記録。
貿易収支は主に、農産物と製造業、サービス収支はハイテク産業だろうから、産業構造は勿論、選挙民の層も地域も異なるだろう。
トランプ大統領の方針は、クリントン政権のときから始めた製造業よりもIT産業を優先し、国の経済を反映させると言う方針の大転換である。IT産業でアメリカ経済は、繁栄を謳歌し続けているが、その一方で、格差は拡大し、製造業を支えるプアーホワイトと言われる人たちの不満を吸い上げると言う点で、民意に沿っていると言える。
もっとも、格差の拡大を関税政策で対処すると言うのは、IT産業がここまで国の経済の大部分を占めている現在、無理ゲーだと言うのが多くの専門家の指摘するところ。また、IT産業への構造転換が遅れた日本にとっては、実はあまり影響がないのではないかと言う指摘もあるがどうなんだろう。
ここからは、私の考えだが、格差の拡大を関税政策による製造業復活と言うのは、国際的なサプライチェーンが複雑に絡み合う現在では、一朝一夕にできるものではない。アメリカの次の中間選挙どころか、任期中にも無理であろう。
宗教的な信仰から来る自己責任論から強い反発があるであろうが、社会福祉等を充実させる方向に持って行くのが解決策の一つだとは思う。その為には、福祉にただ乗りしようとする不法移民の対処も問題になるであろうが。
ハンガリー料理について率直な感想を述べると、レストランで食べるハンガリー料理はおいしくないが家庭料理はびっくりする程おいしい。
例えば前菜は鶏ガラで作った肉スープ、メインは Pörkölt というパプリカで牛肉もしくは豚肉を煮込んだシチューに手づくりのニョッキを付け合わせる。これと薄い輪切りにして甘酢にさらしキュウリサラダが抜群の相性。ちなみ周辺国でメインで食されるグーラッシュは Pörkölt のバリエーションで、ハンガリーの Gulyas はスープ扱い。
トランプが日本に24%の関税を掛けると言っているのは、日本がアメリカに対し46%の関税を掛けているという理由らしい。そんな事実はない訳だが、この46%という数字は日本の貿易黒字額を日本からアメリカへの輸出額で割ったレートとの事。つまり貿易黒字を減らせばトランプ関税も下がるという図式。
GAFA企業が日本で法人税を払わずに挙げている利益を貿易黒字額から引いてもらえないものだろうか。
東欧の本を読んでから、やたらとバルカン半島付近の情報が目につくようになったためか、テレビ番組にも気が付いた。
途中から見たが、ハンガリーが独立を勝ち取った後、その喜びを様々な建築の装飾で表現したこととか、街の美しさとかを取り上げていた。
そう言えば、大阪万博でもハンガリー料理が初日は人気が一番だとかリポートしたテレビ番組があった。
海のない国に、そんなに美味しい料理があるものなのかと思うのは偏見であろうか。
この番組について事前に知人から知らされていたが、時間を間違えて大河を見てしまった。以前はこのような時にアジア系違〇サイトで動画を見つける事ができたが、そういうのは一掃されてしまった模様。予告編と5分間のダイジェスト版のようなドローン映像だけ見れた。
赤沢大臣が交渉するらしいが、日本の取る関税交渉は、
1)個別にアメリカと交渉し、他の国々に抜け駆けと言われようが、さっさと妥協点を決めてしまうやりかたであろうか。アメリカは、ガキ大将的なところがあり、各国と個別に交渉するのを好む。特に、この傾向は、ディールを好むトランプ政権では顕著だ。
アメリカ政府が、日本と初めに交渉すると発表したのは、こうした日本政府の足元を見透かしているからであろう。
2)ガキ大将と対峙するのに一番効果的なのは、多国間交渉にアメリカを巻き込むことだ。ガキ大将のワガママが多数決の論理で抑制できるからである。これが嫌だから、トランプ政権はTPPから離脱した。
多国間交渉を行う為には、他の国々と共同歩調をとり、事前に十分示し合わせなければならない。また、日本は、EU、英国と対等な話し合いができるとは思えないし、上手く利用されてしまう恐れがあるので、これも国益に沿った交渉ができるかは未知数だ。
3)もう一つの方法は、アメリカに代わる貿易相手を探すこと。中国のことが石破政権の念頭にはあると思うが、これも一筋縄ではいかないだろう。一度、中国みたいな国に依存してしまうと、弱みを握られたような状態になり、散々利用されても抜けられなくなる恐れがある。
一方で、長い歴史と地理的状況を考えると、中国と言うのは適度な距離感を持って付き合って損のない国である。ロシアやアメリカよりも、数百年単位で考えれば、信頼できる国とも言えなくはない。
と言うことで、1)の方法で、大臣は、少しいじめられて、半べそかきながら交渉を終え、石破総理がドンマイと慰めると言うふうになるのではないか。
もしも、この過程で希望を持つとしたら、外圧を利用して、日本の農政改革が始まることくらいであろう。
さっきハンガリーの世界遺産を紹介した番組を見ていたが、1867年の独立までは、オスマントルコ帝国に続きオーストリアに支配されていたので、独立時の喜びは大きく、その象徴となる国会議事堂を立派に建造したので、現在は世界遺産になっているとかいう説明だった。考えて見ると、日本は異民族の侵入や支配が殆どなかったが、それでも、白村江の戦いで敗れてから100年以上、そして、弘安の役の後の50年くらいは防人や元寇防塁等、それなりに国防意識が高かった時期がある。
1867年にようやく独立し、それから100年も経たないうちにソ連による抑圧の期間があり、さらに現在でも不法移民の流入に目を光らせる必要がある国では、国境警備や国防、そしてその為の外交に対する国民の意識は異なるんだろうと思う。
それにしては、日本はノンビリしているが、ウクライナみたいにならないか、さすがに心配になってきた。
ポランコは暇に任せて青の掲示板への復帰を目論んでいる。
たけちゃんマンとかにまた気持ちの悪い忖度をしてすり寄るのだろう。
笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
>> 9369
言われて青の掲示板を見てみたら、荒れていた。
本日は、ホラダンス氏の書き込みもあって、雨で中止か。
最近、ホラダンス氏は、朝、チョコっとゴミ出しの後に書き込んでいるようだ。控えめにしたのが、ベイスターズが落ち込まない理由かもしれない。
勝負は下駄を履く迄わからないというのは将に今日の試合。
青の掲示版は大荒れの模様だが、7回92球零点のケイを8回から替えたのは、ケイ自身に何か原因があったと思いたい。開幕前のオープン戦や2軍戦に一時期投げない期間があったのがその根拠。そうではなく、単に石田裕太郎に回跨ぎを再度試させたいという理由なら、オープン戦気分でペナントレースを戦うなと言われてしまう。
梶原があのセンタ~ライナ~を取っていればというのはたらればか。とりあえず連敗は4で止まった。
なるほど。納得。解説ありがとうございます。
明日からのヤクルト戦で、つばみは、どう振る舞うかな
>> 9366
その通り、ストーカーだな、ジャビットは^_^
クルリンパをやったとか。
ナオキの写真を見る限り、ディアナ?に対するストーカー行為かも。
なんだ、ポランコが昨日の試合前に投稿していたとは。どうりで勝ち試合のいい流れが断ち切られた訳だ。
引き分けになった理由は山本と甲斐の勝負所のリードの差もあった。8回の表に山本は追い込んだカウントから外角一辺倒のリードとなり、甲斐に同点打を狙い打たれた。甲斐は9回の裏ピンチの場面、高梨に内角をつかせて筒香を打ち取った。
しかしオ~スティンが抜けた途端にピストル打線もいいところ。去年のあの左の外人と契約延長しなかったなら、代わりを取らないと駄目だろう。
昨日は勝ちゲームを落としてしまった気がしてならない。
久しぶりに青の掲示板を見たら、案の定😩
誰も『いいね』をクリックしていないところから見ると、ミソッカスなのか
昨晩は、久しぶりに勝ちゲームを見られなかったのでは。
ところでジャビットがつば九郎の真似とは? スタジアムに行かないと分からないのかもしれず、すみません。
ジャビット、つば九郎の真似

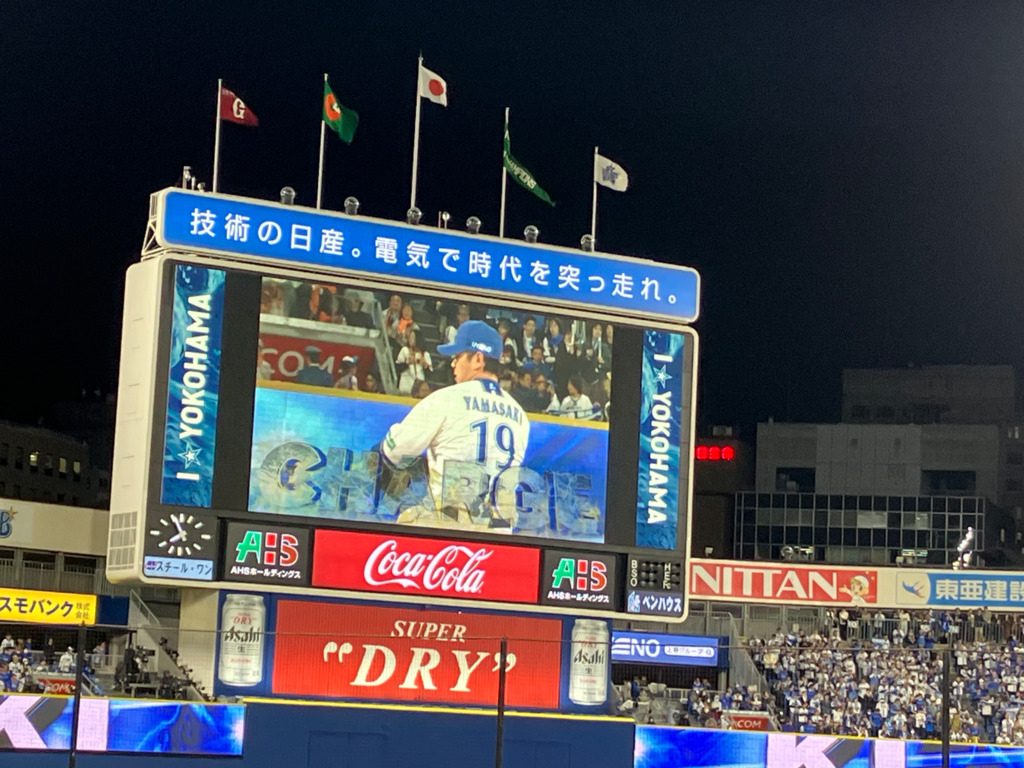
もしハンガリーで何かを思い出すとしたら、世界史で習ったオーストリアハンガリー帝国だろう。東ローマ帝国が滅びてから色々な帝国がエウロパには出現したが、18世紀には共和制の国家、アメリカが出現し、1867年に出来たオーストリアハンガリー帝国は、最後の方の帝国の出現だろう。1867年と言えば、江戸時代の最終章。日本は海に囲まれているから、エウロパとは異なるが、この時に、蝦夷地を統合し大日本帝国としたのと、マジャール人の地域を併合してオーストリアハンガリー帝国としたのは、同じうよなものなのかどうか。大きく異なるのは、日本は万世一系の天皇家が2千年以上も続いているのに対し、エウロパの君主は、日本で言えば武家将軍に過ぎず、征夷大将軍にはなっていない。
最終回、牧、佐野、筒香で三凡とは寂しい。筒香の打撃が一向にあがってこない。昨年、日本シリーズできっかけを掴んだとか言っていたのは何だったのだろうか。捕手が甲斐なので、攻め方も分かっていると思うのだが。
ルーマニアはコマネチ、ブルガリアはヨーグルトが日本人にとってピンと来るところだろう。一方、ハンガリーにはこれと言ったものがない、というか知られていない。初めて行く前はそういうミステリアスなところに惹かれたのかもしれない。それで行ってみて現実を目の当たりにして、大きなショックを受けたのは今や昔。
あ、ホントだ、ハンガリーとブルガリアを間違えていた。失礼。
チェコスロバキアは、ヒトラーがミュンヘン会談で併合したからドイツに近いと分かるが
ルーマニア、ハンガリー、ブルガリアはごちゃ混ぜになっていた。
日曜日に試合に負けると月曜日に試合がないので、負けた悔しさを火曜日まで引きづり嫌だと、南場オーナーが言っていたが、心情はいかに。
これは自分の勘違い。ソフィアに地下鉄が出来たのは割と最近で自分が行った頃はまだなかった。それでいつのまにかブルガリアに地下鉄がない=旧ユーゴにはあるという論理になっていた。しかし旧ユーゴとアルバニアに地下鉄がないというのがこの話題の前提で、2番目の文章のハンガリーもブルガリアを指している。
ちなみにハンガリー、ブダペストの地下鉄の歴史は古く、空港方面へ延びる2号線に旧ソ連製の車両がお色直しされて運用されている。
ん、ハンガリーとブルガリアをまた書き違えている。2番目のくだりは旧ユーゴをハンガリーと言っているようなので、国旗が似ているとかいう問題ではなさそう。あの辺の旧社会主義諸国はいっしょくたに思えてしまうのか。アメリカ第一主義の影響かもね。
去年よく見られた平凡なフライとかなんでもない送球をポロっと落とすのに始まり、デナのエラーはレベルの低いのが多かった。今年はそれに拍車がかかって相手が爆笑もしくは大よろこびしそうな内容になっている。例えば中日戦で筒香がバックホーム送球する代わりにグラブでボールを上に放り上げたり、阪神戦で牧がぼてぼての当たりをとりそこねた挙句すねでボールを蹴ったり。観ていないがこの広島戦でも守乱に陥ったようで、そんな内容のオンパレードでは。
バルカン半島にハンガリーが含まれているか、良く分からなかったのだが、調べたら入っている。
以前も書いたように、地下鉄は、戦時のシェルターの役割を果たすので、バルカン半島でハンガリー以外の国になかったのは意外だった。ウクライナでも、時々、地下鉄の駅に非難する人達の映像が出てくる。
ところで、DeNAも日ハムも守備を強化したと言った割には、失策が多い。野球は、まずは守備から。そして、相手のミスにつけ込むことができるチームが強い。この後、どうなっていくのか、注意深く見守りたい。
ところで、株価が急落しているが、ホラ吹きホラダンス氏はどうしているのだろう。
ブルガリアにはあるね。ソフィアのようにのんびり見える首都に地下鉄が開業している事自体驚きだが。
首都以外に地下鉄のある国に絞れば、イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、ギリシャ、ポルトガルくらい。調べてみたらスイスの首都ベルン及びチューリッヒに地下鉄はなく、ローザンヌにあるとの事。
ベイスターズも日ハムも負けたので、エウロパの地下鉄の話でも投稿しよう

これを見ると、バルカン半島には、地下鉄がないんだな
あの場面、VTRを見てアレっと思ったのは同感。
ネットで記事を調べてみたら、一応,捕手も抗議したようだが、その間にテレビでは、VTRが流れていたのだろう。
ヤスアキは、復活したのか、どうなのか、良く分からない。
いつものように打たれれば、以前からダメだったと後追いの記事が出るであろうし、好調が続けば、その逆であろう。
こういう時には、江川卓氏のポジショントークではない解説等を聞いてみたい。
https://www.ronspo.com/articles/2025/2025040402/
不可解判定?いや“誤審”です…阪神の藤川監督が球審に確認するもファウル判定の1球に泣いて引き分けを挟み3連敗…OBからは「リクエストの適用範囲を拡大すべきでは?」の声も
2025.04.04 07:43
阪神が3日、京セラドーム大阪での横浜DeNA戦に2-5で敗れ引き分けを挟んで3連敗を喫した。焦点となったのは9回一死一塁からハビー・ゲラ(29)が佐野恵太(30)に2-2から投じた1球。明らかに空振りを奪ったが、ファウルの不可解判定を下されて三振が一転、四球となり、直後に勝ち越し点を奪われた。同点で迎えた9回にはクローザー投入のセオリーを無視した藤川球児監督(44)の采配も含めて、物議を醸す虎ファンにとって後味の悪い敗戦となった。
ファウルチップの有無やハーフスイングはリクエストの適用外
不可解判定?いや明らかな誤審だ。
8回に佐藤の起死回生の2号2ランで2-2の同点に追いついた阪神は9回のマウンドにゲラを送り込んだ。一死から宮崎にレフト前ヒットを許して佐野を迎えた。カウント2-2から、ゲラが投じた9球目、外角低めのボールゾーンに落ちるスプリットに佐野のバットは空を切った。だが、今季初スタメンに抜擢された栄枝のミットからボールがこぼれてしまった。ゲラも栄枝も三振だと確信していたが、真鍋球審はファウルの判定を下して、佐野が打席へ戻ったのだ。
栄枝がボールがバットに触れていないことを訴え、藤川監督も静かにベンチから出て、真鍋球審に確認作業を行った。真鍋球審は3人の塁審を集めて協議したが、ファウルチップかどうかは一番近くにいる球審の判断が優先される。しかも、真鍋球審が責任審判。判定が覆ることはなかった。中継局では、繰り返しスロー映像が流れたが、佐野のバットは、まったくボールに触っていなかった。不可解判定どころか誤審である。
だが、リクエストの適用範囲にストライク、ボールの判定やハーフスイング、及びファウルかどうかの判定は含まれていない。メジャーのチャレンジに倣って導入された制度だけに、メジャー同様にそこは適用外の部分。藤川監督もビデオ検証を求めることはできなかった。
だが、この1球が命運を分けた。佐野に11球粘られた末に四球を与え、続く山本に前進守備を敷いていた近本の頭上を抜く、2点タイムリー三塁打を浴びた。さらに1軍に昇格したばかりの伊藤将にスイッチしたが、森の浅いセンターフライでタッチアップを許して3点差。9回も反撃できず引き分けを挟んで3連敗となった。
スポーツ各紙の報道によると藤川監督は、「空振りだと思うんですけどね。すごく大事な1球でしたね」と、この判定に疑問を投げかけたという。
公認野球規則では、抗議は認められていないため、あくまでも確認作業になるが、藤川監督が、執拗に審判に食い下がらなかったのは、ゲラがマウンドで長い時間放置されて調子を崩すことを懸念したのだという。
阪神OBである評論家の池田親興氏は、「映像を見る限り、空振りに見えますが、球審は、ファウルチップの音や目で確認したのではなく栄枝が捕球できなかったということでファウルと判断したのでしょう」とした上で、こう提言した。
「人間が判断することなのでミスがある。それを正す意味でメジャーでチャレンジ制度が始まり、日本も追随した。ただ日本はすべてそのままメジャーの真似をする必要はないと思う。試合の進行を遅らせることになるので、ストライク、ボールの判定は別にして、今日のようなファウルの有無は、リクエストの対象に加えていいのではないか。メジャーのマイナーではストライク、ボールにAI判定が導入され、メジャーでも今季のオープン戦では試験的に使われていた。AI判定に関してもメジャーの後追いをするのではなく日本が独自に先に採用を検討していいのでは?」
確かにリクエスト制度が導入されてもまだ残るグレーゾーンになんらかのメスを入れる必要がある。
ただ今回の不可解な判定に関しては、阪神は意見書をNPBに提出するなど、フロントが抗議行動を見せる必要があるだろう。そして“誤審騒動”に隠れたが、9回にゲラ投入という継投策にも疑問は残った。
セオリーでいえばホームゲームで同点の9回はクローザーを投入する。
岡田前監督は、調子と、相手チームの打線や相性などを見極めながら、岩崎とゲラのクローザーを使いわけていた。時には、岩崎-ゲラの順での起用もあった。だが、藤川監督は、開幕から岩崎をクローザーとして起用してきた。しかも、ゲラは連投で、昨日は、スピードは出ていたが、ストレートは高めに浮き、変化球が制御できず、4安打、3失点していた。セオリーであれば9回は岩崎だったはずだ。
9回はオースティン、宮崎と右打者が続く打順。前日の借りを返させて、いいイメージを取り返すためにゲラを起用したのかもしれないが、腑に落ちない継投策だった。
だが、池田氏は、「この継投策は間違ってはいない」と藤川采配を支持した。
「阪神がクローザーを誰にするかもまだ序盤で手探りだろう。延長を考え、ゲラのブルペンでの調子、打線の巡り、そして長いシーズンを考えて昨日の失敗を取り戻させておきたいなど、様々な理由から藤川監督が判断したんだと思う。ゲラを先に使ったことには、超一流のクローザーだった藤川監督だからこその采配理由があったように感じる。判定の問題もあって結果的に失敗したが、それをもってこの継投が間違いだったとは言えない。十分に考えられる継投策だった」
移動日なしで、今日4日からは東京ドームに乗り込んで昨年のリーグ覇者、巨人との3連戦。開幕2つ目のカードを負け越した藤川監督は、どうチームの舵を取るのだろうか。
今日の阪神戦で勝敗を分けたのは九回表打者佐野の2-2からのスィング。判定はファールチップだが、VTRで見る限りバットにあたっていない。しかし捕手がその投球を捕球できなかった。それで佐野は駄目元でバットに当たったとアピールしたらそれが通ってしまったという事ではないだろうか。そのシーンは画面に映っていなかった。もしそうだとしたら判定後の捕手のリアクションは余りにもあっさりとしていたが。。。
去年59試合投げて抑えもこなし自責点10だった阪神のゲラだが、今年は3試合で早くも自責点6。
ヤスアキは9回の裏150Kを連発していたが、直球の威力が復活したのかはたまたスピードガンのバグか
勝手な思い込みだが、巨人はそのうち、落ちてくるだろうが、阪神に勝っておきたい。
オースティンはジャクソンに、話しかけるであろうか。
昨日の巨人戦に先発した石川が勝ち投手になった。相手が手負いのヤクルトとは言え良く投げたと思う。大きなテークバックからの直球が上ずり気味になるのは相変わらずだったが、緩急が利いていた。
かつてイチローが同時期にメジャーで活躍した長谷川滋利について「小さなテークバックからピュッと球が出てくるので打ちにくい」と言っていたが、その逆バージョンか。
対策としては昨日の中日戦メヒア相手のような早打ちではなく、待球して四球絡みで自滅させたいところ。
**** 記事では確か王は来ても長嶋は来ないとあったと思うが、長嶋茂雄氏には、そう言う配慮があったのかもしれない。選手時代の王には、味方が大量リードしているのにも拘わらず、ちょっと打たれると委縮した新浦投手に対し、「スコアボードを見ろ」と言われたと言う逸話があるらしい。
オースティンの打席以外の挙動は、これまであまり見ていなかったので、これから注意してみようと思う。見逃すかもしれないので、新たな発見があったら教えてください。
新浦は巨人時代「ノミの心臓」と呼ばれていたそうで、投手コーチと捕手に加え長嶋と王を含む野手全員が間近に来ると却ってプレッシャーを掛けるという配慮もあったのでは。
バウアーとオースティンの場合は助人でネーティブ同士なので状況が異なる。オースティンは去年ジャクソンやケイがピンチに陥った時、日本人の輪が解けた後一言二言声掛けしていたように思う。ロペスに至ってはストライクが入らないエスコバ―をどやしつけていた。
巨人にいた新浦投手の連載に書かれていたが、昔、新浦投手がマウンドでピンチになり他の内野手が集まっても長嶋茂雄三塁手だけは来なかったらしい。それは別に新浦が嫌いなわけではなく、プレイに集中していたからだったと新浦は書いていた。オースティンの場合も同様な理由ということはあるであろうか。
チャット GPT に聞いてみたら 不仲ではないということになっていたが。
本日の試合4回の表ノーアウト満塁のピンチの場面。大原投手コーチが通訳と共にマウンドに駆け寄り、内野手全員がバウアーの廻りを囲む。オースティンはというと、最も遠目の位置にいて手持無沙汰ぽさを隠すかのように、マウンドの土を手でならしていた。人の輪が解ける時にバウアーへの声掛けもなし。やはり不仲説は本当なのか?
本日は、大リーグにNPB、選抜高校野球と盛りだくさんだ。
日本では野球は大学野球から始まっており、そして、昔は大学野球が一番の人気だった。
競技名を野球と名付けたのも東京大学野球部だし(正岡子規等、諸説あり)、天皇杯はいまだに六大学野球に授与される。
その次が高校野球で、阪神電気鉄道が甲子園を建造し、無料で高校野球大会のために誘致したのが成功し、現在でも使用料は無料らしい。
甲子園で優勝した時の盾と言うのは、優勝校が入り口に堂々と飾っていたりする。
高校野球の後にようやく戦後になって、六大学野球のスターだった長嶋茂雄氏の活躍等により人気が出来ていたのがNPBで、大リーグに興味を持ち始めたのは近年のことだ。
これらの順序は、現在では、逆になっているのかもしれない。
面白い順に言わせていただくと、高校野球とNPB、それからメジャーと大学野球だ。
メジャーは、内野の守備が堅固過ぎるためなのか、スモールベースボールが少ない。恐らく、作戦として考えると成功の確率が低くなるのではないか。必然的に、長打偏向となる。加えて、ピッチクロックは、見ていて気になって仕方がない。やめてほしい。試合時間短縮の為であれば、高校野球ほどでなくても、打席の交代時の時間を短縮する等、やることはあると思う。
かといってNPBは、少し遅いと思う。この前、ドジャースとカブスの試合を観ていたが、テレビコマーシャルの時間が攻守交替の時間にギリギリ入る感じだった。それだけ、メジャーの方が素早く交代するのであろう。
思うに、NPBでは、投手や打者が構えてから、プレートやバッターボックスを外すのを制限したらよいのではないか。
ところで、高校野球は非常に速いペースで試合が進むため、監督は素早い決断を迫られるそうである。
またまたアメリカネタ。
グリーンランドでは、こんな帽子があるとのmeme。
昔の選手は、大した給料はもらっていないと思う。この前、何かで聞いたが、堀内投手が現役時代、年収500万円くらいだったらしい。(最高のときで1800万円)これでは年金がないと厳しいだろう。特に当時は、所得税の最高税率は高かったし。
鈴木尚典コーチの年収をこの前見たが、選手時代の合計が18億円らしい。活躍に比して随分少ないと思うが、この頃に米田氏が活躍していれば、資産額も違っていたと思う。
それよりも実名でニュースになるのは、常連だったのか、何か特別なことがあったのか。そもそも認知症を疑う投稿もあるが、どうなんだろう。
最近は、甲子園に出場する名門校でも監督が学業や大学進学等にも気を配るようになってきた。岡田元阪神監督も、高校卒業後にすぐに育成契約を結びプロ入りする球児に対して警笛を鳴らしている。
高校卒業後、プロに入った米田氏がどうだったかは知らないが、スポーツ馬鹿だったとは思いたくない。
名球会・殿堂入りしている米田哲也が缶チューハイの万引きで逮捕とは。プロ野球機構に年金制度がないので、充分に貯蓄していない限り老後の生活は苦しいか。
前にも書いたが三浦の良さはベンチで泰然自若としているところ。それ以外の良さは特にないのかもしれない。でもどこか芯が通っていないとあのようには振舞えない。ベンチにどんと座って細かいところはコーチに委ね、選手の自主性を尊重する。フロントがいい選手を集めれはそれで結果は出るはずと思っているのだろう。